事業売却とは?初心者でもわかる流れ・メリット・事業承継との違いをやさしく解説
- FA

- 1月13日
- 読了時間: 10分

▼目次
事業売却とは?初心者でもわかる流れ・メリット・事業承継との違いをやさしく解説
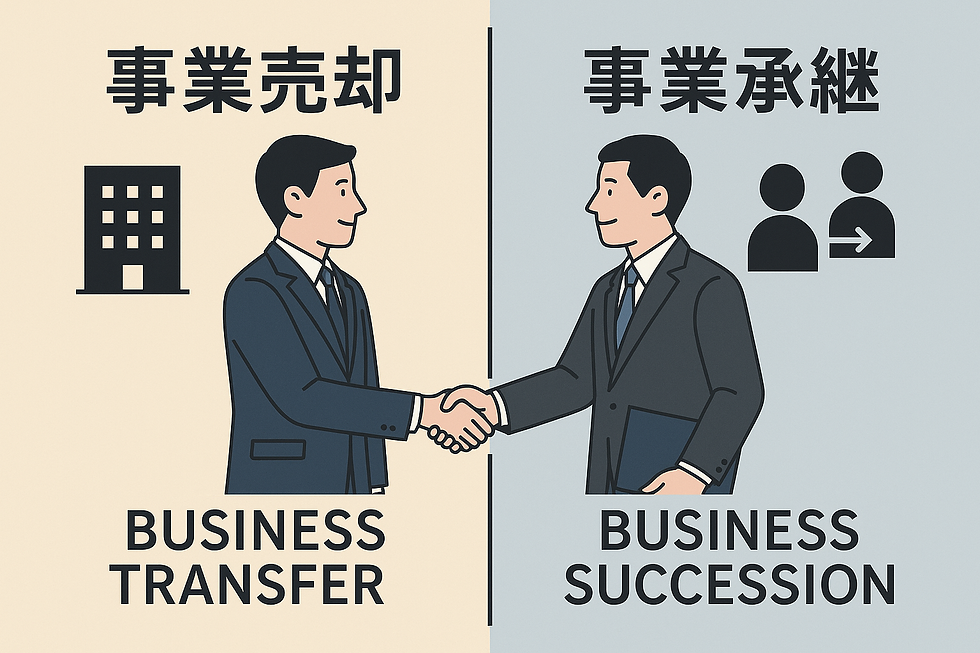
事業売却と事業承継の違いをわかりやすく解説
事業売却と事業承継は似たようなイメージを持たれがちですが、目的も手法も異なります。
事業売却(事業譲渡)とは: 会社の一部(商品部門、技術、人材など)を他社に売ることで、資金調達や経営のスリム化を図る手段です。
事業承継とは: 会社そのものを次世代に「引き継ぐ」こと。親族や従業員、第三者などが経営を受け継ぐ形です。
表で見る!事業売却と事業承継の違い項目 | 事業売却(事業譲渡) | 事業承継 |
目的 | 資金調達/選択と集中 | 経営の継続・後継者問題の解消 |
対象 | 会社の一部(事業単位) | 会社全体(経営権含む) |
買い手/引継ぎ相手 | 他企業 | 親族・従業員・第三者など |
対応年齢層 | 現役経営者も活用可 | 引退・後継準備段階の経営者向け |
主な手段 | 事業譲渡契約 | 株式譲渡・贈与・相続 など |
💡 ポイント:「売却=切り離して現金化」「承継=理念も含めて継ぐ」と考えると、違いがイメージしやすくなります。
事業売却の流れをステップごとに解説【初心者向け】
事業売却は、いきなり売却先と契約するわけではありません。段階的に準備と確認を重ねながら進めていく必要があります。
STEP1:事前準備と現状整理財務状況の整理(決算書や在庫、契約状況の洗い出し)
売却対象事業の棚卸し(何を売却対象とするかを明確に)
専門家(会計士・M&A仲介など)に相談しておくと、スムーズです。
STEP2:売却先の選定仲介会社やM&Aプラットフォームを活用
信頼できる相手かどうか、資金力や事業との相性もチェック
STEP3:基本合意・条件交渉価格、支払い方法、引継ぎ条件などを話し合い
秘密保持契約(NDA)を結ぶ場合も多い
STEP4:デューデリジェンス(精密調査)相手企業が、売却対象の事業に問題がないかを詳細に調査
財務・法務・労務など、あらゆる面を確認されます
STEP5:最終契約と引継ぎ契約締結後、必要書類の作成・名義変更・従業員対応などを実施
場合によっては、一定期間のサポート(経営者の残留)も必要
STEP6:税務・法務対応売却益にかかる税金の処理や、登記の手続きなど
税理士・弁護士のサポートを受けながら進めるのが安心
補足:デューデリジェンスとは?「Due Diligence(DD)」は、買い手側が購入前に行う詳細調査のこと。会社の健康診断のようなものです。
事業売却は、大きな決断を伴うプロセスですが、しっかりと準備し、専門家の力も借りればスムーズに進められます。

事業売却のメリット・デメリットをわかりやすく解説
事業売却は、資金調達や経営の見直しを図るうえで有効な選択肢ですが、一方で注意すべき点もあります。ここでは、経営者が知っておくべきメリット・デメリットを分かりやすく整理します。
事業売却のメリット1. 即時の資金調達ができる
事業を売却することで、現金を短期間で得られるため、資金繰りの改善や新規事業への投資に充てられます。
例:赤字続きの非中核事業を売却し、黒字部門に経営資源を集中することで、全体の収益改善に成功。
2. 不採算事業の整理・撤退ができる
収益性の低い事業や将来性の乏しい部門を手放すことで、経営のスリム化・効率化が可能になります。
3. 従業員の雇用維持につながる場合も
売却先が事業を継続してくれる企業であれば、従業員の雇用を守れる可能性が高いです。廃業よりも雇用維持率が高い点は、大きな安心材料になります。
4. 経営者が次のステージに進める
後継者がいない場合や引退を考えている経営者にとって、事業売却は円満な引き際を実現する手段の一つです。
事業売却のデメリット・注意点1. 売却価格が希望額に届かないこともある
市場環境や買い手企業の評価によっては、想定より低い価格での売却になる可能性もあります。
ポイント:専門家による「事業価値評価(バリュエーション)」を行い、相場観を持っておくことが重要です。
2. 社内・取引先への影響が大きい
売却の発表により、従業員や取引先に動揺が広がることがあります。信頼関係への影響を避けるには、丁寧な説明が不可欠です。
3. 手続きが煩雑で、時間とコストがかかる
契約交渉やデューデリジェンス(詳細調査)、法務・税務の処理など、事務作業が多く、専門家の支援が必要です。
4. 失敗すると「のれん代」がリスクになることも
「のれん(Goodwill)」とは、事業価値に上乗せされるブランドや顧客基盤の価値のこと。過大評価された場合、後でトラブルになるリスクも。
事業売却は、「資金調達」「経営の再構築」「後継者問題の解決」など、多くのメリットがありますが、その一方で慎重な判断と入念な準備が不可欠です。
事業価値の評価、売却先の選定、社員・関係者への説明など、ステップごとにしっかりと対応していきましょう。

事業売却のよくある失敗事例と成功のポイント
事業売却は会社の将来を左右する大きな決断です。うまく進めば資金調達や経営の再構築につながりますが、準備不足や判断ミスによってトラブルに発展するケースも少なくありません。
ここでは、実際にあった失敗例と、それを避けるための成功ポイントを紹介します。
よくある失敗事例1. 価格交渉で損をした
事例:適正な事業価値を把握しないまま売却を進めた結果、相場よりも安い価格で手放してしまった。
原因:自社の強みや資産価値を明確にしておらず、交渉材料がなかった
教訓:**専門家による事業価値評価(バリュエーション)**を事前に受けるべきだった
2. 買い手選びで失敗した
事例:買い手が事業をうまく引き継げず、従業員が不安を抱えて退職者が続出。
原因:事業内容に適さない相手に売却してしまった
教訓:買い手の経営方針・財務状況・業界理解をきちんとチェックする必要がある
3. 従業員や取引先への説明不足で混乱
事例:社内や主要取引先に十分な説明をしないまま売却を進め、信頼関係が悪化。
原因:タイミングを誤った情報開示
教訓:従業員・取引先への丁寧なコミュニケーションが不可欠
4. 税務処理を軽視して思わぬ納税負担に
事例:売却後の利益にかかる税金を見落とし、多額の法人税が発生。
原因:税理士に相談せず独自に手続きした
教訓:税務の影響を事前にシミュレーションし、専門家と対策を練ることが必要
事業売却を成功させる5つのポイント1. 売却の目的とゴールを明確にする
「なぜ売却したいのか?」「売却後にどうなりたいか?」を整理し、ぶれない方針を持ちましょう。
2. 事業価値を正確に把握する
売上・利益だけでなく、ブランド力・顧客基盤・人材も含めて価値を見極めることが重要です。
3. 買い手候補の選定を慎重に
単に「高く買ってくれる相手」ではなく、事業の成長・従業員の将来を託せる相手を選ぶ視点を持ちましょう。
4. 専門家の力を活用する
M&A仲介、会計士、税理士、弁護士などの専門家と連携することで、法務・税務・価格交渉などをスムーズに進められます。
5. 社内外への説明・対応を怠らない
従業員や取引先への信頼関係を壊さないよう、情報開示のタイミングや内容を慎重に設計することが大切です。
ワンポイントアドバイス:事業売却は「単に売る」ことが目的ではなく、「次のステージへの橋渡し」と考えることが成功のカギです。
事業売却を考えたら活用したい専門家・支援制度
事業売却は、一度きりの大きな決断になることが多く、法務・税務・交渉など複雑な手続きが関わります。成功の鍵は“専門家のサポート”と“活用できる公的制度”を上手に使うことです。
ここでは、事業売却時に頼れる専門家の種類と、公的支援制度について紹介します。
まずは誰に相談すべき?3つの専門家1. M&A仲介会社・アドバイザー
事業売却の全体をサポートしてくれる存在です。
売却先の紹介・マッチング
価格交渉・契約支援
スケジュール管理・クロージングまでの進行
信頼できる仲介会社を選ぶためには、手数料体系・実績・専門性を事前にチェックしましょう。
2. 会計士・税理士
事業売却に関する会計処理や税金対策のプロ。
売却益にかかる法人税・所得税のシミュレーション
節税スキームの提案
財務デューデリジェンスの支援
売却後に思わぬ税負担が発生しないよう、早い段階から相談するのがおすすめです。
3. 弁護士
売買契約書や機密保持契約(NDA)の作成・確認を担当。
法的リスクのチェック
契約条項の調整・交渉
紛争・トラブル時の対応
特に契約書の内容は売却後のトラブル防止につながるため、必ず法的な視点で確認してもらいましょう。
知っておきたい!公的な支援制度・相談窓口1. 中小企業庁「M&A支援機関登録制度」
信頼できるM&A支援機関を選ぶための公的制度。登録された支援機関は一定の質を担保しており、第三者承継支援補助金の対象にもなります。
2. 事業承継・引継ぎ支援センター(各都道府県に設置)
後継者問題や売却を考える中小企業を無料で支援してくれる公的窓口です。
専門家とのマッチング支援
事業価値の簡易診断
売却の基本相談・事例紹介 など
地方の小規模企業でも安心して相談できるのが特長です。
3. M&A補助金(第三者承継補助金)
一定の条件を満たせば、事業売却にかかる専門家への費用の一部を国が補助してくれる制度です。
補助額:最大500万円程度(年度により変動)
対象経費:仲介手数料、デューデリ費用、契約書作成費用など
事業売却は「情報量」と「判断スピード」が成功のカギ。ひとりで悩まず、信頼できる専門家や支援制度を早めに活用することが大切です。
特に「後継者がいない」「経営資源を集中させたい」などの課題を抱える経営者の方は、事業が元気なうちから準備を始めるのが成功の近道です。

事業売却に関するよくある質問
Q1. 事業売却と会社売却(株式譲渡)はどう違うのですか?A.事業売却は、会社の一部(店舗、サービス、商品部門など)を他社に売る方法で、会社そのものは存続します。一方、株式譲渡による会社売却は、会社全体の経営権を手放す形です。
Q2. 売却にかかる期間はどれくらいですか?A.一般的に、6か月〜1年程度が目安です。売却対象の規模や条件交渉の難易度、相手の選定状況によって変動します。
Q3. 赤字事業でも売却できますか?A.はい、可能です。たとえ赤字でも、ブランド力・技術・人材・顧客基盤などの価値に魅力があれば、買い手が見つかることもあります。
Q4. 売却先はどうやって探せばいいですか?A.M&A仲介会社や事業承継・引継ぎ支援センター、公的マッチングサイトなどを通じて探す方法があります。信頼できる支援機関に相談するのが成功の近道です。
Q5. 売却で得た資金には税金がかかりますか?A.はい、売却益には法人税や所得税がかかる場合があります。詳細はケースによって異なるため、税理士に事前相談するのが安心です。
まとめ|事業売却で経営の可能性を広げよう
事業売却は、「経営の失敗」ではなく、新たなステージに進むための戦略的な選択肢です。特に以下のような経営者にとって、有効な一手となります。
不採算部門から撤退し、収益事業に集中したい
後継者不在の問題を解決したい
新規事業へ投資する資金を確保したい
自社のリソースを再編し、持続可能な成長を目指したい
事業売却を成功させるには、早めの準備と信頼できる専門家のサポートが不可欠です。公的支援制度も積極的に活用し、自社にとってベストな形で次の一歩を踏み出しましょう。





コメント