法人税とは?法人税率の種類と法人税の計算方法をわかりやすく解説【2025年最新版】
- FA

- 7月7日
- 読了時間: 7分
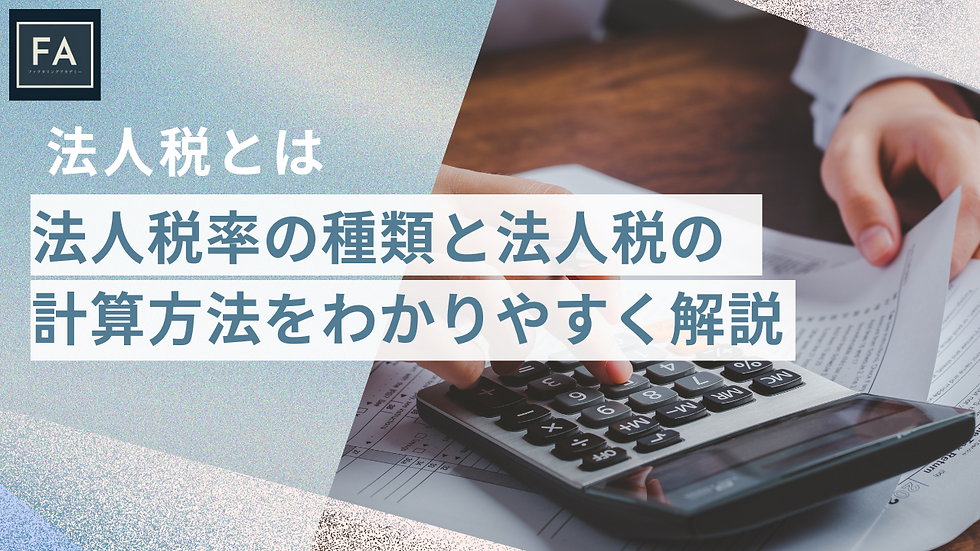
目次法人税とは?法人税率の種類と法人税の計算方法をわかりやすく解説【2025年最新版】
法人税とは?個人所得税との違いと仕組みを解説
法人税の定義と目的法人税とは、株式会社や合同会社など法人格を持つ組織が、事業で得た利益に対して納める国税です。会社が1年間に得た所得(=利益)に対して課税され、所得税と同様に累進的に税率が設定されています。
法人税の目的は、企業活動から得られる利益に公平に課税し、国の財政を支えることにあります。
個人の所得税との違い個人が納める「所得税」は個人の収入に対して課されますが、「法人税」は法人が得た利益に課税されます。また、個人は累進課税(収入が増えるほど税率も上がる)なのに対し、法人税は一律の税率(基本は23.2%)で課されます。
誰が対象になるのか?(課税対象となる法人)法人税の課税対象となるのは、以下のような法人です:
株式会社・合同会社・合資会社・合名会社などの営利法人
協同組合、医療法人、NPO法人など一部の非営利法人(収益事業に対して)
公益法人や財団法人も、収益事業を行っていれば課税対象になります
法人税率の種類と中小企業の税率【2025年版】
法人税の基本税率現在、日本の法人税の基本税率は以下の通りです:
課税所得 | 法人税率(国税分) |
800万円以下 | 15%(中小企業特例) |
800万円超 | 23.2% |
これはあくまで「法人税」の税率であり、地方税を含めた実効税率は約30%前後になります。
中小企業特例の軽減税率資本金1億円以下の中小法人は、年800万円以下の所得に対して15%の軽減税率が適用されます。中小企業にとっては大きな節税効果があるため、適用条件を確認しておくことが重要です。
法人住民税・事業税・地方法人税の概要と税率法人の納める税金は法人税だけではありません。実際には以下のような税もあわせて発生します:
法人住民税:都道府県・市町村に納める税(法人税額×〇%+均等割)
法人事業税:所得に応じた地方税。一定額を超えると外形標準課税の対象
地方法人税:国に納めるが地方に配分される税金
これらを含めると、実効税率は約30%〜34%程度になります。

法人税の計算方法を具体例で解説
法人税の計算は複雑な印象がありますが、流れをつかめば理解しやすくなります。ここでは法人税の基本的な計算ステップと、実際の金額例を用いてわかりやすく解説します。
法人税の計算ステップ法人税の計算は、以下のステップで行われます:
税引前当期純利益を確定する(会計ベース)
会計上の利益から「加算・減算調整」を行い、課税所得を算出する
損金不算入(交際費の一部など)→ 加算
損金算入(減価償却費、役員報酬など)→ 減算
課税所得に法人税率を掛けて法人税額を算出する
地方税(法人住民税・事業税・地方法人税)を加えて、納税総額を確定する
計算例(年間利益1,000万円のケース)例として、年間の税引前利益が1,000万円の中小企業(資本金1,000万円以下)で、特別な調整がない場合の税額を見てみましょう。
項目 | 金額(概算) |
税引前利益 | 1,000万円 |
課税所得(調整なしと仮定) | 1,000万円 |
法人税(800万円までは15%、残りは23.2%) | 800万円×15%+200万円×23.2% = 約184万円 |
法人住民税(法人税×約14%、均等割7万円と仮定) | 約32万円+7万円 = 約39万円 |
法人事業税・地方法人税 | 約50万円(課税所得に応じて変動) |
合計納税額(実効税率:約27〜30%) | 約270万円前後 |
※あくまでシンプルな例です。実際は交際費、減価償却、繰越欠損金、特別控除など多くの要素が関わります。
税引前利益と法人税等の関係性(損益計算書とのつながり)法人税は損益計算書(PL)の「税引前当期純利益」からスタートします。この利益に対して税額が決まり、支払う税金が差し引かれた後、「当期純利益」が確定します。
企業の利益は“見かけの利益”であり、法人税を含む税金を差し引いた後の**実質的な利益(可処分利益)**が手元に残る金額です。正しい利益管理と法人税の理解は、資金繰りや経営判断に直結します。

法人税の納付スケジュールと申告の流れ
法人税は、一定のスケジュールに従って「申告」と「納付」を行う義務があります。期限を過ぎると延滞税や加算税が発生するため、しっかりと把握しておくことが大切です。
確定申告と中間申告の時期法人の納税には「確定申告」と「中間申告」の2種類があります。
区分 | 内容 | 期限 |
確定申告 | 決算期の終了後に、1年間の利益に基づいて税額を確定・申告・納付する手続き | 決算日から2カ月以内(原則) |
中間申告 | 事業年度の中間で予定納税を行う制度(前年度の法人税額が10万円超の場合) | 事業年度開始から6カ月を経過した日から2カ月以内 |
※申告期限が休日と重なる場合は、翌営業日が期限となります。
納付方法と納税先(電子申告の対応も)法人税の納付は以下の方法で行えます。
電子納税(e-Tax):インターネットバンキングやクレジットカード決済も可能
金融機関の窓口:指定の納付書を使用して支払う方法
税務署への持参:原始的だが対応可能(非推奨)
現在は**電子申告(e-Tax)**の利用が一般的で、税理士に依頼する場合も電子での申告・納付が主流となっています。

節税対策としての法人化メリットとは?
法人化には法人税が発生する一方で、節税の選択肢が広がるというメリットもあります。個人事業主から法人成りを検討している方にとって、節税は重要な判断材料です。
法人税の節税ポイント以下のような支出が損金として計上できるため、節税効果が期待できます。
役員報酬(個人の所得税と分散できる)
社会保険料
福利厚生費(社員旅行、健康診断など)
経費(家賃、車両費、通信費など)
特に、所得が高い場合は法人税の方が税負担が軽くなるケースも多く見られます。
役員報酬や経費計上による節税法人化の節税テクニックとして代表的なのが、「役員報酬の活用」と「経費の適切な計上」です。
役員報酬を支払うことで、会社の利益を減らし法人税を抑える
家事関連費を経費とする場合は明確な区分が必要(私的流用はNG)
税務調査でもチェックされやすいポイントなので、税理士など専門家の指導を受けながら計上することが重要です。
税理士に相談するメリット法人税は制度が複雑で、適用ミスによる過大納税や税務リスクも生じやすいため、税理士に相談することで以下のようなメリットが得られます。
正確な税額計算と適切な節税提案
税務署対応(申告・調査など)の代行
最新の税制改正に対応したアドバイス
顧問税理士がいない場合は、無料相談サービスなどを活用して比較検討するのもおすすめです。
まとめ|法人税は「仕組み」と「計算手順」を理解すれば怖くない
法人税は一見すると難解に思えるかもしれませんが、基本的な構造や計算ステップを理解すれば、適切な対策や準備ができるようになります。
特に中小企業や個人事業主が法人化を検討する際には、「どのくらいの税金がかかるのか」「節税できる余地はあるか」を事前に把握しておくことが重要です。
以下のようなポイントを押さえておきましょう:
法人税は利益に対して課税される国税(住民税や事業税も合わせて納税が必要)
中小企業には軽減税率の特例がある(15%)
法人税の計算は「損益計算書の利益」から税務調整を行って算出する
節税対策や申告の正確性を高めるためにも、専門家(税理士)との連携が有効
経営者として最低限の知識を身につけつつ、不明点は税理士に相談することで、より賢く法人経営が行えるようになります。





コメント