リバースファクタリングとは?利用する際のメリット・デメリットや通常ファクタリングとの違いを解説
- FA

- 1月13日
- 読了時間: 10分
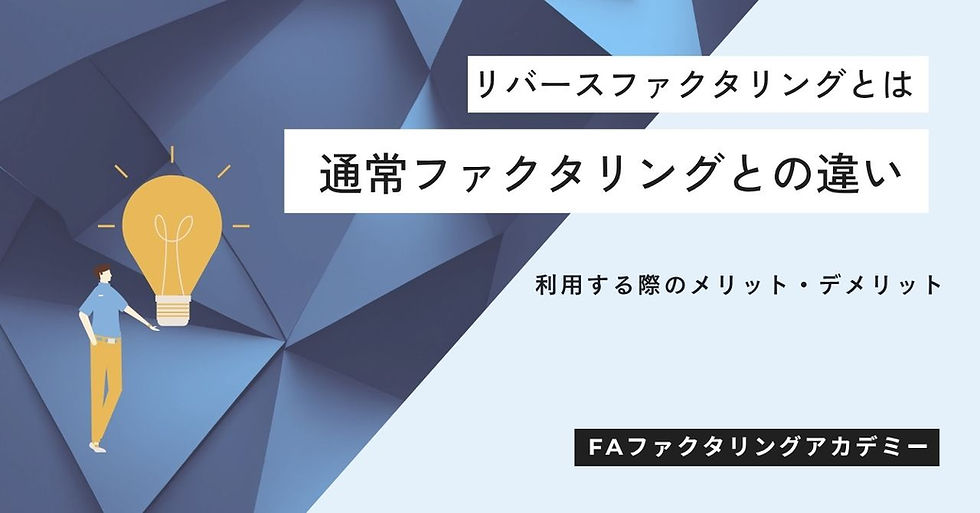
▼目次
リバースファクタリングとは?利用する際のメリット・デメリットや通常ファクタリングとの違いを解説

リバースファクタリングとは
仕組みと通常ファクタリングとの違いリバースファクタリングとは、発注企業(バイヤー)が金融機関やファクタリング会社と提携し、自社が発注した取引先の請求書を早期に支払うことで、下請企業(サプライヤー)の資金繰りを支援する仕組みです。
通常のファクタリングでは、売掛債権を保有する企業(売り手)がファクタリング会社と契約し、資金を早期に受け取るのに対し、リバースファクタリングは、買い手企業の信用力を活用して取引先が資金を得る点が特徴です。
【通常ファクタリングとの違い】
主導者が異なる:通常ファクタリングは売り手主導、リバースファクタリングは買い手主導。
信用力の使い方が違う:売り手の信用力ではなく、買い手の信用をもとに資金化される。
利用目的:リバースは主に取引先の支援・関係強化を目的とする。
リバースファクタリングが注目される背景近年、企業間の取引における支払いサイトの長期化や、サプライチェーン全体の資金繰り悪化が問題視される中、下請企業の資金調達を効率化する方法としてリバースファクタリングが注目されています。
また、DX化の進展や、銀行・ファクタリング業者との連携によって、導入のハードルも徐々に下がっており、大企業を中心に活用が広がりつつあります。

リバースファクタリングのメリット
リバースファクタリングには、発注企業(バイヤー)と取引先企業(サプライヤー)の双方にとってメリットがあります。ここでは、それぞれの立場からの利点を紹介します。
サプライヤー側のメリット資金繰りの安定化 リバースファクタリングを利用することで、通常よりも早く売掛金を回収できるため、キャッシュフローが改善します。特に支払いサイトが長い契約を結んでいる場合、大きな効果を発揮します。
信用力に依存しない資金調達 通常のファクタリングではサプライヤー自身の信用力が審査対象になりますが、リバースファクタリングでは発注企業の信用力を活用するため、自社の財務状況にかかわらず資金調達がしやすくなります。
借入ではないため、財務への影響が小さい 資金調達でありながら借入ではないため、貸借対照表上の負債に計上されず、財務健全性を維持しやすいのもメリットです。
バイヤー(発注企業)側のメリット取引先の支援による関係強化 下請企業の資金繰りを支援することで、パートナー企業との信頼関係が深まり、長期的な取引の安定につながります。
サプライチェーンの安定化 取引先が資金繰りで倒産するリスクを低減できるため、自社の調達体制にも良い影響を与えます。
支払いサイトを変更せずにキャッシュフローを維持可能 発注企業は支払い期日を変えることなく、サプライヤーには早期入金を可能にする仕組みのため、両者の資金計画を両立できます。
リバースファクタリングのデメリット・注意点
便利な仕組みである一方、リバースファクタリングにはいくつかのデメリットや導入時の注意点も存在します。導入を検討する際は、事前に以下の点を把握しておくことが重要です。
導入の手間とコストシステム導入や業務設計が必要 リバースファクタリングを利用するには、専用のシステム導入や社内業務フローの見直しが必要になる場合があります。特に買い手企業側では社内調整が必要です。
初期費用・利用手数料が発生 金融機関やファクタリング業者との契約において、利用手数料や導入支援費用などのコストが発生することがあります。
サプライヤー側の制約利用できる企業が限定される リバースファクタリングは、あくまで発注企業が提携先としてファクタリング業者と契約している場合に限り利用可能です。そのため、すべての取引先に使えるわけではありません。
対応業者がまだ少ない 一般的なファクタリングと比べ、対応可能なファクタリング会社は限られており、選択肢が少ないのが現状です。
バイヤー側の責任とリスク支払い義務が前提となる契約 発注企業が最終的な支払責任を負う仕組みであるため、与信リスクや資金計画を慎重に見直す必要があります。
すべての取引先に適用できるとは限らない サプライヤーの同意が必要なため、導入してもすべての下請企業にスムーズに適用できるとは限りません。
通常のファクタリングとの違い【比較表付き】
リバースファクタリングは、通常のファクタリングとは仕組みや主導者が大きく異なります。どちらも「売掛金の早期資金化」を目的としていますが、導入目的や活用方法に違いがあります。
以下に、両者の主な違いを比較表でまとめました。
ファクタリングとリバースファクタリングの違い【比較表】項目 | 通常ファクタリング | リバースファクタリング |
主導者 | 売り手企業(サプライヤー) | 買い手企業(発注元・バイヤー) |
信用力の基準 | 売掛先(買い手)の信用力 | 買い手企業自身の信用力 |
利用目的 | 自社の資金繰り改善 | 取引先の資金繰り支援、サプライチェーン安定化 |
契約関係 | 売り手企業とファクタリング会社 | 買い手企業とファクタリング会社(+売り手企業) |
支払いサイト | 変更される可能性あり | 買い手側の支払期限はそのまま |
費用負担 | 売り手企業が負担することが多い | 買い手企業が負担することが多い |
財務への影響 | オフバランス処理可能(場合による) | サプライヤー側は借入扱いにならず財務に優しい |
対象企業の規模感 | 中小企業・個人事業主向けが多い | 発注元が大企業であることが多い |
利用ハードル | 比較的低い | 導入に事前準備が必要 |
補足ポイント
通常ファクタリングは自社主導で手軽に始めやすい一方、手数料や信用審査に影響されやすい傾向があります。
リバースファクタリングは発注企業の支援策として有効で、特に複数の取引先を抱える大手企業にとってはサプライチェーン全体の資金安定化に寄与します。

リバースファクタリングが向いている企業
リバースファクタリングはすべての企業に適しているわけではなく、特に一定の条件を満たす企業において高い効果を発揮します。ここでは、発注企業(バイヤー)側と下請企業(サプライヤー)側それぞれに向いている企業の特徴を解説します。
向いている発注企業(バイヤー)以下のような企業は、リバースファクタリングの導入に適しています。
多数のサプライヤーと継続的な取引をしている企業 複数の取引先を抱えている企業では、取引全体の安定化とリスク分散の観点から、サプライヤー支援の仕組みとして効果的です。
財務体質が安定している中堅〜大企業 リバースファクタリングでは、発注企業の信用力が資金化の根拠となるため、信用格付けや財務状態が良好であることが望まれます。
サステナビリティやCSR(企業の社会的責任)を重視している企業 取引先の資金繰り支援は、社会貢献活動や取引先との良好な関係構築にもつながります。
向いている下請企業(サプライヤー)サプライヤー側としてリバースファクタリングの恩恵を受けやすいのは、次のような企業です。
資金繰りに悩んでいる中小企業や地方企業 自社の信用力では資金調達が難しい場合でも、発注企業の信用を使うことで早期入金が可能になります。
特定の大手企業との取引依存度が高い企業 メインクライアントがリバースファクタリングに対応していれば、その取引で発生した売掛金を安定的に資金化できます。
支払いサイトが長く、キャッシュフローに負担がある業種 建設業・製造業・物流業など、取引から入金までの期間が長くなりがちな業種において特に有効です。

リバースファクタリング導入の流れと注意点
リバースファクタリングを導入する際には、段階的な準備と関係者間の連携が必要です。以下に導入までの一般的な流れと、注意すべきポイントをまとめます。
導入の一般的な流れ(発注企業側)ファクタリング業者・金融機関の選定 まずはリバースファクタリングに対応した専門業者または銀行との連携を検討します。
契約・業務フローの設計 利用するスキームに応じて契約を締結し、社内業務フローを構築します。
サプライヤーへの導入提案と同意取得 対象となる取引先に対して制度の説明と同意を得る必要があります。
運用開始・モニタリング 実際の取引において運用を開始し、状況に応じた調整や改善を継続します。
導入時の注意点全ての取引先が対応できるとは限らない 特に小規模なサプライヤーでは制度の理解や書類対応に不安があるケースもあります。
情報管理や業務の煩雑化に注意 複数の取引先と契約する場合、運用負担が増すため、専用の管理体制やツールが必要です。
社内調整と経営層の理解が必要 財務・経理部門だけでなく、調達部門や経営層と連携しながら導入を進めることが成功の鍵です。

よくある質問
Q1. リバースファクタリングを利用する際の手数料はどのくらいですか?A. 手数料は契約するファクタリング会社や金融機関、取引条件によって異なりますが、年率1〜3%程度が相場です。バイヤー側が負担するケースが多いため、サプライヤーにとっては無料で利用できる場合もあります。
Q2. リバースファクタリングと通常のファクタリングは併用できますか?A. はい、併用可能です。ただし、同じ売掛債権に対して両方を同時に適用することはできません。用途や取引先ごとに使い分けるのが一般的です。
Q3. サプライヤー側は特別な契約や手続きが必要ですか?A. ファクタリング会社によって異なりますが、基本的にはバイヤー側との合意を前提に、簡易な登録・同意手続きで済む場合が多いです。大きな負担なく導入できる点もメリットのひとつです。
Q4. どのような業種での活用事例がありますか?A. 製造業、建設業、物流業、IT業界など、売掛金の支払いサイトが長くなりやすい業種で導入が進んでいます。また、商社や流通業など、多数のサプライヤーを持つ企業でも導入事例があります。
Q5. リバースファクタリングを導入する際の注意点は?A. 導入には社内調整やサプライヤーとのコミュニケーションが必要です。また、業務フローやシステム構築の初期コストも考慮して、全体のスキームを理解した上で導入することが大切です。
まとめ|リバースファクタリングはサプライチェーン強化の新たな選択肢
リバースファクタリングは、通常のファクタリングとは異なり、発注企業が主導して取引先の資金繰りを支援する仕組みです。発注企業にとっては取引先との関係強化やサプライチェーンの安定化を図ることができ、サプライヤーにとっては信用力に左右されずに早期資金化が可能となる、双方にメリットのあるファイナンス手法といえます。
ただし、導入にあたっては体制整備や業務設計、サプライヤーとの合意形成など慎重な準備が必要です。自社にとって適したスキームかどうかを見極めた上で、専門業者や金融機関と連携し、段階的に導入を進めることが成功のカギとなります。
リバースファクタリングは、企業の持続可能な成長とサプライチェーン全体の健全化を実現する「新たな選択肢」として、今後ますます注目されていくでしょう。





コメント