売上高経常利益率とは?【わかりやすい計算方法と業種別平均の目安】
- FA

- 1月13日
- 読了時間: 14分

企業の経営状態を正しく把握するうえで欠かせない指標のひとつが 「売上高経常利益率」 です。「利益率が低いと危険なのか?」「業界平均と比べて自社はどうなのか?」「計算方法がよくわからない」――経営者や経理担当者からこうした声をよく耳にします。
売上高経常利益率は、単なる数字ではなく、会社がどれだけ効率よく利益を生み出しているか を示す重要なものです。金融機関の融資判断や投資家の評価指標としても活用されており、正しく理解することで経営改善のヒントが得られます。
本記事では、
売上高経常利益率の基本的な意味
誰でもできる計算方法
業種別の平均値と目安
改善するための具体策
を、初心者にもわかりやすく解説します。最後まで読めば、自社の強み・弱みを客観的に分析でき、今後の経営戦略に活かせるはずです。
▼目次
売上高経常利益率とは?【わかりやすい計算方法と業種別平均の目安】

売上高経常利益率とは何か ― 意味と使いどころ
企業の収益力を測る指標にはさまざまなものがあります。その中でも 「売上高経常利益率」 は、会社全体の本質的な収益力を把握できる重要な指標のひとつです。
売上高経常利益率とは、企業が売上高に対してどれだけの経常利益を稼ぎ出しているかを示す割合のことです。たとえば、売上高が10億円、経常利益が1億円ならば、売上高経常利益率は 10% という計算になります。
この指標は、日常の営業活動だけでなく、金融収支や持株の配当収益などを含めた「本業+財務活動全体」の結果を反映しているため、会社の総合的な稼ぐ力を示すものといえます。
営業利益率との違いは?
営業利益率は「売上高に対して営業利益がどの程度あるか」を示す指標で、本業の収益性だけを測ります。これに対して売上高経常利益率は、営業利益に加えて金融収支などを含めるため、会社全体の安定性を評価するのに適しています。
経常利益を用いるメリットとは?
金融費用(利息など)の影響を含められる
本業に加え、副次的な収益・費用も考慮できる
銀行や投資家が企業の「本当の収益力」を見る際に使いやすい
経営判断における重要性
売上高経常利益率が高いほど、景気変動や借入金利の上昇といったリスクに強い体質といえます。そのため、銀行融資の審査、株主への説明、企業価値の評価 にも広く利用されています。

売上高経常利益率の計算方法を徹底解説
売上高経常利益率の計算はシンプルですが、正しく理解することが重要です。
経常利益の定義と算出式
経常利益は以下の式で求められます。
経常利益 = 営業利益 + 営業外収益 − 営業外費用
営業外収益には、受取利息や配当金、投資有価証券売却益などが含まれます。営業外費用には、支払利息や為替差損などが含まれます。
売上高経常利益率の算出式
売上高経常利益率は以下の式で計算されます。
売上高経常利益率(%) = 経常利益 ÷ 売上高 × 100
実際の数値例で解説
例:売上高10億円、営業利益8,000万円、受取利息500万円、支払利息1,500万円の場合
経常利益 = 8,000万円 + 500万円 − 1,500万円 = 7,000万円
売上高経常利益率 = 7,000万円 ÷ 10億円 × 100 = 7%
この企業の売上高経常利益率は7%となり、業種平均と比較することで経営の強み・弱みを判断できます。
⚠️注意すべきポイント
営業外収益や費用の影響で大きく変動することがある
一時的な収益や特別損益は含まれないため、継続的な収益力を評価できる
借入金が多い会社は支払利息が重く、利益率が低くなりやすい
業種別の平均値はどれくらい?業界ごとの目安一覧
売上高経常利益率は 「業種によって大きく異なる」 指標です。飲食業や小売業はどうしても薄利多売のビジネスモデルになりやすく、利益率は1%前後しかないのが一般的です。一方、不動産や情報通信業、専門サービス業は利益率が高く、10%を超えるケースも珍しくありません。
まずは業種ごとの目安を一覧表で確認してみましょう。
業種別の平均値(目安一覧)
業種 | 売上高経常利益率の平均(目安) | 特徴・補足 |
学術研究・専門サービス業 | 約12.0% | 専門知識・技術を売る高付加価値型。人件費は高いが粗利率も高い。 |
不動産業 | 約9.5% | 資産ビジネス型。利息負担は重いが、賃料収益が安定している。 |
情報通信業(IT・ソフト) | 約8.0% | 固定費は高いが、スケールすれば収益率は急上昇。 |
製造業 | 約5.0% | 業種によりバラつき大。自動車や化学は5~7%程度が一般的。 |
卸売業 | 約2.0% | 流通を担う中間業。売上規模は大きいが利益は小さい。 |
小売業 | 約1.5% | 典型的な薄利多売モデル。大量販売でカバーする。 |
飲食業 | 約1.0% | 価格競争激化、人件費・原材料費高騰で低水準。 |
運輸業(物流・陸運など) | 約1.5% | 燃料費・人件費の影響大。景気や規制に左右されやすい。 |
業種ごとの特徴と背景
小売・飲食業利益率は低いですが、回転率の高さとキャッシュフローの安定性でカバーしている業種です。経常利益率1%でも、売上が数百億円規模であれば十分に利益を確保できます。
製造業設備投資が重い分、売上高経常利益率は平均5%前後。ただし、**高付加価値型(精密機器・医薬品)**は10%超えも可能。逆に低価格競争が激しい業種は3%を切ることもあります。
不動産業賃料収入や売却益で大きな利益を稼げるため利益率は高めですが、借入依存度が高いため金利上昇に弱いという特徴があります。
情報通信業初期投資や研究開発費が重い一方で、成功すれば利益率は一気に跳ね上がります。SaaSやクラウドサービスのようなストック型モデルは特に高収益。
学術研究・専門サービス業弁護士、会計士、コンサルティング業など、知識集約型の産業は人材が主なコスト。粗利率が高く、平均で10%超え。
業種間の差が生まれる理由
固定費構造の違い製造業や運輸業は設備・燃料費が重く、景気変動に敏感。一方、専門サービス業は知識やスキルに依存するため高収益。
資金調達の違い不動産業のように借入依存度が高い業種は、利息負担の大小が利益率に直結。
競争環境の違い飲食業や小売業は価格競争が激しく、値上げが難しいため低収益に留まりやすい。
自社を平均と比較する際の注意点
業種の特性を踏まえて評価する飲食業で「3%」ならかなり優秀、不動産で「3%」なら平均以下、というように同業種の平均との比較が必須です。
単年度ではなくトレンドで見る一時的な為替差益や金利動向で上下するため、3~5年の推移で見ることが重要です。
規模とのバランスを見る利益率は低くても、売上規模が大きければ十分な利益を確保できます。逆に利益率が高くても売上が小さいと事業リスクが高い場合もあります。

売上高経常利益率を改善するための具体施策
売上高経常利益率が低いからといって、すぐに「赤字」「危険」と判断する必要はありません。ただし改善に向けて具体的なアクションをとることで、安定した収益体質へと近づけることができます。
改善の切り口は大きく分けて ①売上の拡大、②コストの削減、③資金調達・財務改善 の3つです。ここからは、それぞれの具体施策を詳しく見ていきましょう。
コスト構造の見直し(固定費・変動費の最適化)
固定費の削減
本社移転やオフィス縮小、テレワーク導入で家賃・光熱費を削減
ITツール導入で人件費・バックオフィス業務を効率化
仕入・原価の見直し
複数仕入先を比較し、価格交渉で調達コストを下げる
在庫回転率を高め、廃棄・滞留在庫の削減
外注費・広告費の最適化
効果測定を徹底し、費用対効果の低い施策を削減
インフルエンサーマーケティングやSNS活用で広告単価を下げる
✅ 成功事例:ある飲食チェーンでは、電力プランを見直すだけで年間数千万円規模のコスト削減に成功。経常利益率を0.5ポイント改善した。
売上・収益源を強化する(トップラインの改善)
高付加価値商品の開発・販売
利益率の高い商品ラインを強化し、売上ミックスを改善。
例:製造業がOEM中心から自社ブランド製品へシフト。
価格戦略の見直し
適正な値上げ(値下げ回避)による単価向上
値引き依存を減らすための「付加価値型提案営業」
新規顧客の獲得・チャネル拡大
EC化、サブスクモデル導入で安定的収益を確保
海外市場や新セグメントへの参入
✅ 成功事例:ITサービス企業がサブスクリプション型に転換したことで、売上高は横ばいでも経常利益率が5%→12%に改善。
財務体質の改善(金融費用を抑制)
借入金利の引き下げ
銀行との交渉や借換えで金利を0.5%引き下げるだけで、大規模借入のある企業は利益率に直結。
資産効率の改善
遊休資産や低収益部門を整理し、資本効率を高める
不要な在庫や余剰現金を適切に運用
為替・金利リスクの管理
為替予約・スワップ契約を活用して急激な損失を回避
✅ ポイント:特に借入依存度の高い「不動産業」「建設業」では、金利負担が1%変動するだけで利益率が数ポイント動くため、財務改善の効果が大きい。
指標の見える化と社内浸透
売上高経常利益率は、経営者だけでなく現場全員が意識できるようにすることが重要です。
KPIとして四半期ごとにモニタリング
部署ごとに「経常利益率改善目標」を割り振る
社内会議で定期的に公表し、改善事例を共有
→ 数値が「現場の行動」に落ちることで、継続的な改善サイクルが回りやすくなります。
短期・中期・長期の改善アプローチ
短期(1年以内)
広告費・外注費のカット
金利交渉・借換え
在庫削減
中期(1~3年)
高付加価値商品の投入
サービスの価格戦略転換
生産ラインや業務プロセスの効率化
長期(3年以上)
ビジネスモデル自体の転換(例:一時的な売切型→ストック収益型)
DX投資による根本的な効率改善
海外進出やM&Aによる事業ポートフォリオ最適化
利益率改善の効果を試算してみる
例えば、売上高100億円・経常利益率2%の企業があるとします。
現状:経常利益=2億円
借入利息を▲5,000万円削減できた場合→ 経常利益=2.5億円→ 経常利益率=2.5%(+0.5ポイント改善)
このように「小さな改善が率に大きく効く」ことを示すと、経営層・社員の意識改革にもつながります。

売上高経常利益率の実務での活用例
売上高経常利益率は「計算して終わり」の数字ではなく、経営判断や資金調達、投資の場面で直接活用できる指標です。ここでは具体的にどのような実務で役立つのかを解説します。
銀行融資の審査における評価指標
金融機関は融資審査において、返済能力を確認するために 売上高経常利益率を重視 します。
利益率が安定して高い企業 → 「借入金利の交渉が有利」「借入枠を広げやすい」
利益率が低迷している企業 → 「融資審査が厳しくなる」「金利が高めに設定される」
例:製造業で経常利益率が平均5%前後のところ、自社が7%を維持できていれば、金融機関に対して「競争優位性がある」とアピールできる。
経営計画・中期経営ビジョンでの活用
経営者は中期経営計画を立てる際に、売上高経常利益率を 目標値として設定 するケースが多いです。
「3年後に経常利益率を3% → 5%に改善」
「同業他社平均を上回る水準を維持」
このように具体的な数値目標をKPIに据えることで、部署ごとの取り組みが明確になります。
💡ポイント:営業利益率だけでなく経常利益率を目標にすることで、財務面(利息・資本効率)の改善活動も促される。
同業他社や業界平均との比較・ベンチマーク
売上高経常利益率は、競合分析や業界研究に欠かせない指標です。
上場企業は有価証券報告書で数値を公開しているため比較が容易
「自社の利益率=業界平均+1pt」を目標とする企業も多い
利益率が大きく乖離している場合、構造的な強み・弱みの発見につながる
例:小売業で平均1.5%に対し、自社が0.8%なら「仕入原価が高い」「販管費が膨らんでいる」など改善テーマが浮き彫りになる。
投資家・株主への説明資料に活用
IR(投資家向け広報)や株主総会の資料では、売上高経常利益率を示すことで 「総合的な収益力」 をアピールできます。
投資家はROEや営業利益率だけでなく、経常利益率を見て安定性を評価する
数字が改善している企業は「成長+安定」の両面で評価されやすい
株価や企業価値の向上にもつながる
社内マネジメント・KPI管理での活用
経営層だけでなく、現場レベルでも経常利益率をKPIとして活用することが可能です。
部署ごとに「利益率改善目標」を設定
四半期ごとに数値をモニタリングし、改善策を共有
粗利率や営業利益率と並べて、**財務コストも含めた“最終的な稼ぐ力”**を可視化
実務Tip:管理会計上は「営業外収益・費用を配賦」し、部門別の“準・経常利益率”を算出することで、各部署の財務意識が高まる。
無料で使えるツールとテンプレート紹介
売上高経常利益率は、数式自体はシンプルですが、毎月/四半期で管理するとなると意外と面倒です。そこで便利なのが、無料で利用できるツールやテンプレート。手軽に導入できるので、会計初心者から中小企業の経営者まで幅広く活用できます。
Excel・Googleスプレッドシートのテンプレート
特徴
売上高・営業利益・営業外収益・営業外費用を入力するだけで自動計算
複数年度・複数月の比較も可能
条件付き書式で「目標を超えたら緑」「下回ったら赤」など色分けができ、直感的に把握できる
活用シーン
月次決算レビューで「利益率の推移」を確認
社内会議や取締役会での報告資料作成
金融機関に提出する資料のベースに
無料テンプレ例
中小企業庁「経営自己診断シート」
会計事務所やコンサルティング会社が公開しているExcelシート
オンライン計算ツール
特徴
ブラウザに数値を入力するだけで即計算できる
スマホ対応ツールも多く、外出先や会議中にその場で試算可能
平均値やベンチマークと比較できる機能付きのものもある
活用シーン
金融機関担当者との打ち合わせ中に即数値を提示したいとき
顧客や取引先に「利益率がどの程度か」を説明する際の参考値に
無料ツール例
freee、マネーフォワードなどクラウド会計サービスの一部機能
経済産業省や商工会議所の経営診断ページ
会計ソフトやクラウドサービス
特徴
決算データから自動で経常利益率を算出
ダッシュボードで「前年同期比」「業種平均」と比較表示
グラフ化されるため社内共有に最適
活用シーン
スタートアップや中小企業が、日次・週次で財務を確認する
CFOや管理部門が投資家説明資料を作成する際の基礎データとして利用
無料プラン例
freee 会計(一定条件下で無料試用可能)
弥生会計オンライン(体験版あり)
オープンデータ・統計資料
売上高経常利益率は「業種別平均値」との比較が重要。無料で利用できる統計資料を活用すれば、自社の立ち位置がすぐにわかります。
代表例
中小企業庁「中小企業実態基本調査」
総務省統計局「企業統計調査」
帝国データバンク/東京商工リサーチの公開レポート(一部無料公開)
これらの統計はプレゼン資料や金融機関への説明資料に引用可能。信頼性が高いデータとして評価されやすい。
⚠️利用時の注意点
自社の会計基準に合わせる
→ 単体決算か連結決算かで数値が異なるため、統一して比較する必要があります。
一時的な特殊要因は除外して分析
→ 為替差益や投資売却益などの「イレギュラー収益」で数値が高く出る場合は調整を忘れないこと。
継続的に記録する習慣化
→ 単発で計算するのではなく、毎月入力・四半期レビューを行うことで経営改善につながります。
よくある質問

Q1:営業利益率と経常利益率、どちらを重視すべき?
A:どちらも重要です。営業利益率は本業の強さを測り、経常利益率は財務面も含めた総合的な収益力を示します。
Q2:利益率が低いと必ず危険?
A:必ずしもそうではありません。業種の特性やビジネスモデルによって適正水準は変わります。
Q3:改善の第一歩は何をすべき?
A:まずはコスト構造を可視化し、固定費と変動費を切り分けることです。そのうえで売上拡大策を検討しましょう。
まとめ:経常利益率を理解し、経営改善のカギを手にしよう
売上高経常利益率は、会社の本当の収益力を測る大切な指標です。
計算式はシンプル(経常利益 ÷ 売上高 × 100)
業種別平均と比較することで立ち位置を把握できる
改善策は「コスト削減+収益拡大」の両輪で進めることが重要
この記事をきっかけに、自社の利益率を定期的にチェックし、より安定した経営につなげてください。




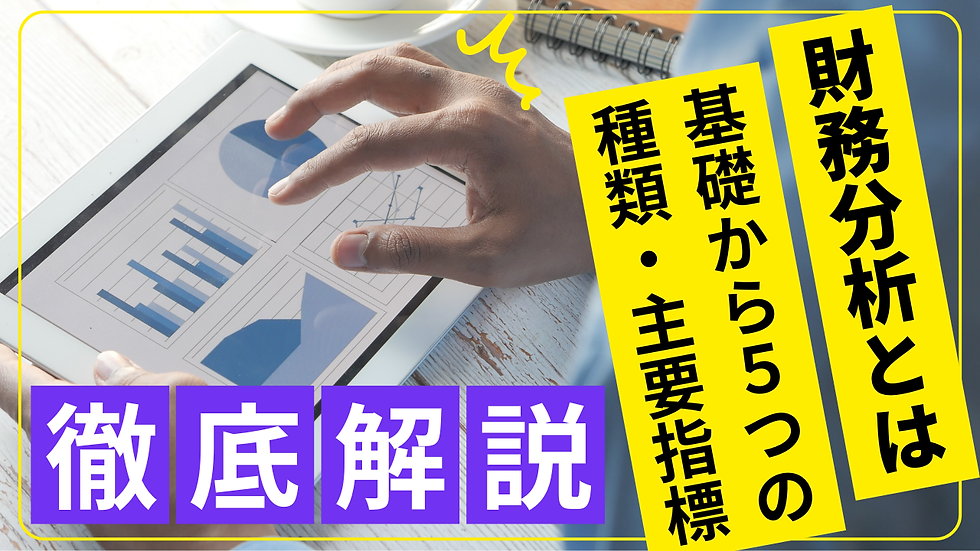
コメント