法人の税金の種類と申告期限についてわかりやすく解説【2026年最新版】
- FA

- 1月13日
- 読了時間: 6分

▼目次
法人の税金の種類と申告期限についてわかりやすく解説【2026年最新版】

法人が支払う税金の種類とは?
法人が負担すべき税金には、国に納める「国税」と、都道府県・市区町村に納める「地方税」があります。ここでは、代表的な6種類の税金を順番に見ていきましょう。
1.法人税法人税は、企業が得た利益(所得)に対して課される国税です。法人の規模や所得によって税率が異なり、通常は以下のような構成になります。
年800万円以下の所得:15%(軽減税率)
年800万円超の部分:23.2%
赤字の法人であっても、将来的な利益と相殺する「繰越控除制度」などが使えるため、正確な申告が必要です。
2.地方法人税地方法人税は、法人税の申告額に連動して課される税金で、国税として一緒に納付します。法人税の税額に一定割合(約10.3%)を乗じて算出される仕組みです。申告や納付の手続きは法人税と同時に行います。
3.法人住民税法人住民税は、都道府県や市区町村に納める地方税です。法人住民税は以下の2つで構成されます。
均等割:利益の有無に関わらず課される定額の税金(資本金や従業員数に応じて変動)
法人税割:法人税額に連動して算出される部分
たとえ赤字でも均等割は必ず発生するため、資金計画に注意が必要です。
4.法人事業税法人事業税も地方税の一種で、都道府県に対して納める税金です。法人の所得に応じて課税されますが、資本金が1億円を超える企業は「外形標準課税」が適用されるケースがあります。
外形標準課税では、所得だけでなく「付加価値額」や「資本等の額」に基づいて課税されるため、大企業にとって負担が大きくなる傾向にあります。
5.消費税消費税は、商品やサービスの提供に伴って発生する税金で、取引先から預かった消費税を国に納める役割を法人が担います。一定の売上高(年間1,000万円)を超えると、消費税の課税事業者となり、申告と納付が必要です。
2023年から導入された「インボイス制度」により、請求書の形式や保存要件が厳格化されています。
6.その他(源泉所得税・印紙税・固定資産税など)事業の内容や規模に応じて、以下のような税金が発生することもあります。
源泉所得税:役員報酬や外注費の支払い時に発生
印紙税:契約書などの文書に課税される
固定資産税:不動産や設備を保有している場合に発生
これらは定期的な納付ではないため、漏れのない管理が求められます。

法人税などの申告・納付期限まとめ
法人が納める税金には、それぞれ決まった申告・納付の期限があります。期限を過ぎるとペナルティが発生する可能性があるため、スケジュールを把握しておくことが重要です。以下は代表的な税目ごとの期限一覧です。
税金の種類 | 申告期限 | 納付期限 |
法人税 | 決算日から2ヶ月以内 | 申告期限と同日 |
地方法人税 | 法人税と同様 | 法人税と同様 |
法人住民税 | 決算日から2ヶ月以内 | 申告期限と同日 |
法人事業税 | 決算日から2ヶ月以内 | 申告期限と同日 |
消費税 | 決算日から2ヶ月以内(課税期間終了後) | 原則申告期限と同日 |
※延長申請を行えば、法人税等の申告期限を1ヶ月延ばすことができます(ただし、納付期限は延長されません)。
ワンポイント:中間申告・納付とは?
売上規模の大きい法人などは、年1回の申告・納付に加えて「中間申告・中間納付」が必要な場合があります。特に以下のような法人は注意が必要です。
前年度の法人税が20万円超:中間納付が必要
消費税課税売上高が4,000万円超:年3回の中間申告が必要

申告期限に遅れるとどうなる?延滞リスクとペナルティ
税金の申告・納付を期限までに行わなかった場合、以下のような罰則や追加費用が課されます。
延滞税・加算税が発生期限を過ぎた納税には、「延滞税」が日割りで加算されます。また、無申告や過少申告があった場合は「加算税」も課されることがあります。
税目 | 遅延の内容 | ペナルティ内容 |
納付遅れ | 納付期限を過ぎた | 延滞税(年利換算で最大14.6%程度) |
申告忘れ | 無申告のまま放置 | 無申告加算税(15〜20%) |
過少申告 | 誤って少なく申告 | 過少申告加算税(10〜15%) |
融資審査や税務調査に悪影響税金の滞納や無申告状態は、金融機関の信用調査や税務署の監視強化につながることがあります。特に、決算書に「未納税金」が記載されていると、融資審査で不利になるケースも少なくありません。
e-Taxや税理士の活用で期限管理を提出期限の管理には、国税庁の「e-Tax」や、市販の会計ソフト、税理士との顧問契約を活用するのが効果的です。申告期限が近づくとアラートが出たり、電子申告で即時提出が可能となるため、うっかりミスの防止にもつながります。
中小企業・個人事業主が気をつけるべきポイント
法人税の仕組みは、企業の規模や業種によって異なる点も多くあります。特に中小企業や個人事業主が法人成りしたばかりのケースでは、見落としがちな注意点も。以下ではよくある落とし穴と対策を紹介します。
資本金1億円以下の優遇措置を活用する中小法人(資本金1億円以下)は、法人税率が軽減されたり、外形標準課税が適用されないなどの優遇措置を受けられます。これらの制度を正しく理解し、適用要件を満たすことで、税負担の軽減につながります。
均等割は赤字でも必ず発生たとえ赤字でも、法人住民税の「均等割」は毎年支払わなければなりません。例えば、資本金1,000万円以下の東京都内法人では年間7万円前後が発生します。赤字経営でも納税資金の準備を怠らないようにしましょう。
資金繰り表で税金支払いを「見える化」する納税資金の確保には、毎月の資金繰り計画が重要です。税金の支払い時期を見える化し、資金不足に陥らないようにしましょう。特に消費税や法人税の納付月には、運転資金がひっ迫しやすいため注意が必要です。
まとめ|法人税の種類と申告期限を押さえて正しく対応しよう
法人が支払う税金には、法人税、地方法人税、住民税、事業税、消費税など多岐にわたります。それぞれに異なる税率や納付スケジュールがあるため、正確な知識とスケジュール管理が必要不可欠です。
特に中小企業や設立間もない法人では、申告漏れや納付遅れによって思わぬペナルティが発生することも。日頃から税理士との連携や会計ソフトの活用、資金繰りの見える化を徹底し、余裕を持った納税体制を整えておきましょう。



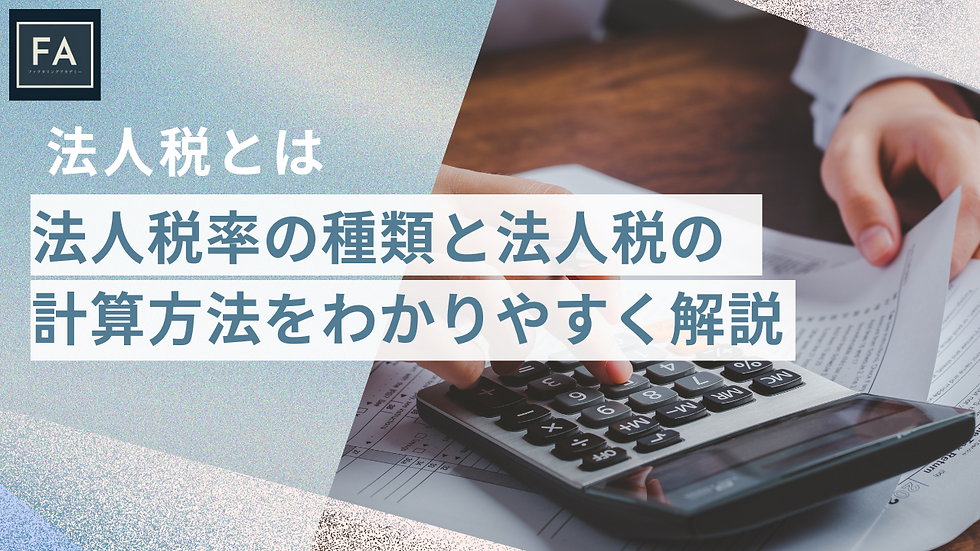

コメント