【2025年対応】売掛金の消滅時効は何年?新民法の期間と回収リスク対策を徹底解説
- FA

- 8月29日
- 読了時間: 11分

はじめに – 売掛金回収の落とし穴「消滅時効」とは?
企業間取引では、納品後に代金を後払いとする「掛取引(売掛金)」が一般的です。しかし、請求しても取引先が支払わないまま一定期間が経過すると、債権者が法的に回収できなくなるリスクが生じます。これが**「消滅時効」**です。
2020年4月1日に施行された民法改正により、この消滅時効制度は大きく見直されました。改正前は「業種ごとにバラバラで、しかも非常に短い時効(2年〜3年)」が多かったのに対し、改正後は原則 「5年」または「10年」 に統一されています。
この改正によって、請求権の保護は強化されましたが、同時に「放置してはいけない」ことが明確化されました。特に中小企業にとっては、売掛金が回収できないことは資金繰りに直結し、経営危機を招きかねません。
本記事では、
売掛金の消滅時効の基本的な仕組み
新旧民法の違いと実務への影響
時効完成を阻止するための具体策
実際の事例とチェックリストを初心者でも理解できるよう、図解や例を交えて解説します。
目次【2025年対応】売掛金の消滅時効は何年?新民法の期間と回収リスク対策を徹底解説
売掛金の消滅時効とは?基礎から解説
消滅時効の基本ルール
消滅時効とは、一定期間の経過により「法律上の権利が消える」仕組みです。売掛金のような「債権」にも時効があり、支払い請求を行わずに放置していると、法的に権利が主張できなくなります。
ポイントは次の3つです。
時効は権利を行使できる状態からカウントされる
期間が経過しても、自動的に消えるわけではない→ 債務者が「時効を援用(主張)」することで効力が発生します
時効完成を防ぐ手段が存在する→ 更新・完成猶予によって進行をリセット/停止できる
改正前と改正後でどう変わった?時効期間の比較
改正前(旧民法)の短期消滅時効
改正前は業種ごとに短期消滅時効が存在しました。
商人間の売掛金 → 2年
弁護士・医師・公認会計士の報酬債権 → 3年
工事請負代金 → 5年
つまり、取引先が支払わない場合、たった2年で時効が成立してしまうケースが多かったのです。
改正後(新民法)の消滅時効
改正後は「一律化」と「柔軟化」が進みました。
主観的起算点:「権利を行使できることを知った時から5年」
客観的起算点:「権利を行使できる時から10年」→ どちらか早い時点で時効完成
実務上は、売掛金の場合 支払期日翌日から5年 が原則です。
表:新旧民法の消滅時効比較
区分 | 旧民法(2020年3月まで) | 新民法(2020年4月以降) |
商人間の売掛金 | 2年 | 5年(主観的起算点) |
請負代金 | 5年 | 5年 or 10年 |
報酬債権(弁護士など) | 2~3年 | 5年(統一) |
原則的扱い | 業種ごとに異なる | 原則5年、一律化 |
売掛金の起算点をどう判断するか?

売掛金の消滅時効を考えるうえで、「いつからカウントが始まるのか」=起算点の判断は非常に重要です。誤った解釈をしていると、気づかないうちに時効が完成して回収できなくなるリスクがあります。
基本ルール
支払期日がある場合→ 支払期日の翌日からカウント
支払期日が明記されていない場合→ 契約成立日(納品完了日や請求可能日)の翌日からカウント
支払期日が明記されている場合
請求書や契約書に「支払期限」が明示されているときは、その期日の翌日が起算点です。
例:
請求書に「支払期日:2021年6月30日」と記載
起算日:2021年7月1日
消滅時効:2026年6月30日
注意点:期日が「月末払い」や「翌月末払い」となっている場合は、実務上は「その月の末日」を基準に起算点を判断します。
支払期日が記載されていない場合
契約や請求書に支払期日がない場合、法律上は「債権発生時=直ちに請求できる状態」になった翌日が起算点です。
契約日:2021年5月31日
請求可能日:即日
起算日:2021年6月1日
消滅時効:2026年5月31日
実務での注意点:期日がないと「どの時点から5年か」が不明確になりやすいため、企業間取引では必ず支払期日を定めることが望ましいです。
分割払い・継続取引の場合
分割払い契約 → 各支払期日ごとに個別に起算点がスタート
継続的取引(例:毎月納品) → 各回の取引ごとに起算点が生じる
つまり、「まとめて1本」ではなく「取引ごと」に時効が進行する点に注意が必要です。
実務で見落としやすいポイント
請求書を発行し忘れた場合でも、時効は進む→ 請求書がなくても債権は発生しているため注意。
口頭契約の場合→ 書面がなくても契約成立日から起算されるため、証拠を残していないと立証が難しい。
部分的な支払いがあった場合→ 債務の承認にあたり、時効が「更新」されてゼロからカウントし直し。
時効完成を阻止する方法(更新と完成猶予)

「5年で権利が消える」とは言っても、実務では時効を阻止する手段があります。
時効の更新
時効をリセットし、再スタートさせる行為。
代表例
裁判を起こす
強制執行を申し立てる
債務者が一部返済する、支払いを認める
これにより、再びゼロから5年がスタートします。
時効の完成猶予
時効を一時的に止める制度。
代表例
催告(内容証明郵便で督促) → 6か月猶予
仮差押え
協議による合意書面
つまり、時効が迫っている場合でも、一手間で権利を守れるということです。
実務での具体例とトラブル事例
売掛金の消滅時効は、単に「5年」というルールを知っているだけでは不十分です。実際の取引では、請求漏れや管理不備、取引先の意図的な主張によって回収できなくなるケースが少なくありません。ここでは、典型的な事例を紹介しながら、注意すべきポイントを解説します。
請求放置による時効完成
A社(製造業)は2020年に取引先B社へ500万円分の商品を納品。請求書を発行したものの、入金が確認できないまま放置してしまった。
問題点
経理担当者が期日管理をしておらず、督促も行わなかった
取引先の経営不振により、支払い能力が低下していた
結果
2025年に回収を試みたが、B社が「すでに時効を迎えている」と主張。裁判所でもその主張が認められ、債権は消滅。500万円が丸ごと回収不能となった。
教訓
債権管理を「属人的」に任せると危険。必ずシステムやリマインダーを使って期日管理を徹底することが必要。
内容証明郵便で時効完成を阻止できた事例
C社(建設業)は取引先D社からの入金が滞り、支払期日から4年11か月が経過。残債は300万円。
対応
顧問弁護士に相談し、内容証明郵便で督促状を送付
これにより、6か月間の「完成猶予」が発生
その間に分割払いの合意書を締結し、債務者が承認
結果
時効は「更新」され、再度ゼロから5年のカウントがスタート。最終的に2年かけて全額回収に成功。
教訓
「あと数か月で時効」という場面でも、内容証明郵便や合意書で延命できる。対応スピードが結果を左右する。
部分入金による時効更新
E社は2021年にF社へ1,000万円を販売。支払い遅延が続き、2025年に一部(100万円)の入金があった。
結果
債務者による「承認」とみなされ、時効がリセット(更新)。残りの900万円も請求可能に。
教訓
「少額でも受け取ること」に意味がある。部分入金は債務承認になるため、必ず記録を残すこと。
口頭契約で証拠不足により敗訴
G社は2020年にH社へコンサルティングを提供。契約は口頭で行い、請求書のみ発行。
問題点
契約書がなく、支払期日も明示されていなかった
裁判で「いつ債権が発生したか」が不明確
結果
裁判所は「起算点が特定できないため、債務者の主張する時効成立を認める」と判断。結果、回収不能となった。
教訓
契約は必ず「書面化」し、支払期日を明記する。口頭契約や曖昧な請求は、証拠不十分で不利になる。
継続取引で一部だけ時効成立
I社はJ社へ毎月商品を納品。2020年6月〜2021年5月までの売掛金合計1,200万円が未回収。
誤解
I社は「取引全体で時効が進む」と考えていた。
結果
裁判で「各取引ごとに個別に時効が進行する」と判断され、2020年6月分(100万円)はすでに時効完成。残りは回収可能だったが、一部損失が発生。
教訓
継続取引でも「各請求分ごとに時効」がある。請求日ごとに管理する必要がある。
よくある質問(FAQ)

Q1. 売掛金の消滅時効は必ず5年ですか?
A. 原則は5年ですが、例外的に10年となるケースもあります。民法改正により、売掛金は「主観的起算点(権利を行使できることを知った時から5年)」と「客観的起算点(権利を行使できる時から10年)」の両方が規定されました。つまり「5年または10年、どちらか早い方」で時効が成立します。実務上は、取引先との支払期日が定まっていれば、ほとんどのケースで5年が適用されます。
Q2. 時効は自動的に成立しますか?
A. いいえ、自動的には成立しません。時効は「債務者が時効を援用(主張)」した時点で効力を持ちます。つまり、5年経過しただけでは債権は消えません。しかし、裁判で相手方が「すでに時効です」と主張した場合、裁判所がその主張を認め、回収が不可能になるのです。
Q3. 分割払いを承認させると時効はどうなりますか?
A. 債務者が一部でも支払いを承認した場合、「時効の更新」となります。例えば1,000万円の売掛金があり、支払期日から4年11か月が経過した時点で相手が100万円を支払った場合、残り900万円の時効もリセットされるのです。これは債務者の「承認」とみなされるため、債権者にとって有利な仕組みです。
Q4. 内容証明郵便で本当に時効を止められますか?
A. はい、内容証明郵便による「催告」で時効の完成を6か月間猶予できます。ただし、注意点があります。
猶予されるのは 最大6か月間
その間に「訴訟提起」や「合意書作成」など次の手続きが必要
放置すると再び時効が進行
したがって、内容証明郵便はあくまで「時間を稼ぐ手段」であり、根本的な解決には法的対応や合意が欠かせません。
Q5. 継続取引の場合、時効はどう数えますか?
A. 各取引(請求分)ごとに時効が進行します。例えば「毎月納品して毎月請求」のような継続取引では、1回ごとの取引ごとに起算点があり、それぞれで5年の時効が動きます。そのため、「古い分だけ時効完成して回収できないが、最近の分は請求可能」というケースが実務で多発します。
Q6. 契約書がなくても時効は進みますか?
A. はい、契約が口頭で成立していても、法律上は債権が発生しています。そのため、契約書がなくても時効はカウントされます。ただし裁判で争う場合、起算点を証明できる書面がないと「時効成立」と判断される恐れがあります。契約や支払期日は必ず書面化しておくことがリスク回避につながります。
Q7. 時効を過ぎても回収できる可能性はありますか?
A. 基本的には回収できませんが、相手が「時効援用」をしなければ任意に支払われることもあります。ただし、裁判を起こされた場合は相手が援用すれば確実に消滅します。期待せず、時効が完成する前に必ず対応することが鉄則です。
Q8. 売掛金回収の時効管理を効率化する方法はありますか?
A. はい、実務では以下の方法が推奨されます。
請求書管理システムや会計ソフトで自動的に支払期日を管理
債権回収代行サービスを利用
一定期間以上滞納があれば、すぐに弁護士へ相談
システム導入や外部サービスの活用によって、人的ミスを減らし「気づかないうちに時効完成」という事態を防げます。
まとめ|売掛金の消滅時効を正しく理解し、早めの対応を
売掛金の消滅時効は原則5年(最長10年)2020年の民法改正で、従来の「2年」などの短期消滅時効が廃止され、原則5年に統一されました。
起算点は「支払期日翌日」または「契約翌日」契約書や請求書に支払期日を明記していないと、起算点が曖昧になり、時効完成を見逃すリスクがあります。
「更新」と「完成猶予」で時効は止められる裁判、内容証明郵便、分割払い合意、債務者の承認などによって時効の進行を止めたりリセットしたりできます。
実務では「放置」が最大のリスク継続取引や口頭契約など、証拠や管理体制が不十分だと、気づかないうちに時効完成し、回収不能になるケースが多いです。
債権管理体制の整備が経営の安定につながる会計ソフトや管理システムを導入し、支払期日・入金確認・督促対応を自動化・仕組み化することが重要です。
売掛金は「取れるはずのお金」ではなく、適切に管理しなければ消えてしまう資産です。時効を正しく理解し、期限前に対応する習慣をつけることで、資金繰りリスクを大幅に減らせます。
「取引先が支払わない」「請求しても放置されている」といった状況に直面している方は、迷わず早めに専門家や債権回収サービスに相談しましょう。



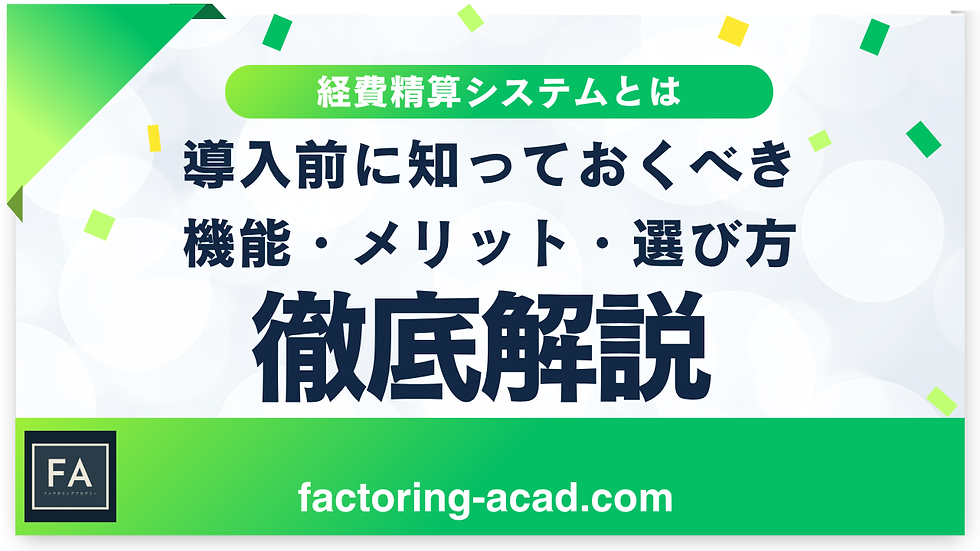

コメント