組織マネジメントの7Sとは?初心者でもわかる7つの要素と活用方法【事例付き解説】
- FA

- 1月13日
- 読了時間: 11分

▼目次
組織マネジメントの7Sとは?初心者でもわかる7つの要素と活用方法【事例付き解説】

組織マネジメントの基本と「7S」とは?
そもそも組織マネジメントって何?組織マネジメントとは、会社や団体などの組織を、同じ目標に向かって効果的に動かすための「運営方法」のことです。たとえるなら、会社はサッカーチームのようなもの。監督(経営陣)が戦術(戦略)を考え、選手(社員)の配置や役割を決め、試合(市場競争)に勝つための動きを整えるのが組織マネジメントです。
もし戦術があいまいで、選手がバラバラに動いていたら、ゴールはなかなか決まりません。逆に、戦術・配置・連携が整っていれば、同じ戦力でも勝てる確率はぐっと上がります。
「7S」モデルとは?マッキンゼーが考えた組織管理のフレームワーク
7Sモデルは、世界的コンサルティング会社マッキンゼーが開発した組織を分析・改善するためのフレームワークです。特徴は、組織の要素を「7つのS(英単語)」に分類し、それらのバランスを見直すことで組織全体を強くする点にあります。
7つの要素Strategy(戦略)
Structure(組織構造)
System(システム)
Shared Value(共通の価値観)
Style(スタイル)
Staff(人材)
Skill(スキル)
これらはハードの3S(比較的すぐ変えられる要素)とソフトの4S(時間をかけて育てる要素)に分かれます。

「7S」の7つの要素を解説【事例&改善方法付き】
ハードの3Sとは?(即変えやすい「外側」の仕組み)1. Strategy(戦略)
意味:会社が目指す方向や長期的な計画。
例:
「国内シェアNo.1を目指す」
「海外市場に進出する」
「AIを活用した新サービスを展開する」
改善方法:
明確な数値目標(売上、シェア率など)を設定する
3〜5年先を見据えたロードマップを作る
社員全員に戦略を共有する場(全社ミーティングなど)を設ける
事例:ある食品メーカーは「健康志向市場に特化」という戦略を打ち出し、全商品を減塩・低カロリーにリニューアル。売上が前年比120%に伸びた。
2. Structure(組織構造)
意味:役割や責任の分担、部署の配置など。
例:
営業部、開発部、広報部のような部署分け
プロジェクト型チーム(案件ごとにメンバーを組む)
改善方法:
戦略に合わせて組織図を見直す
部署間の連携をスムーズにするための中間役職を設ける
プロジェクトごとに専門チームを編成する
事例:通販企業が「EC専門部署」を新設。既存店舗とは別のKPIを設定し、オンライン売上を1年で2倍にした。
3. System(システム)
意味:業務を効率化するルールや仕組み。
例:
勤怠管理システム
経費精算のルール
営業進捗の報告方法
改善方法:
紙ベースの作業をデジタル化
社内マニュアルを作成し、誰でも同じ手順で業務ができるようにする
定期的に運用ルールを見直す
事例:建設会社がクラウド勤怠管理を導入し、集計時間を月30時間削減。人事部の残業が大幅に減少した。
ソフトの4Sとは?(時間がかかる「内側」の文化や人)4. Shared Value(共通の価値観)
意味:会社全体が大切にしている理念や信念。
例:
「お客様第一主義」
「チャレンジ精神」
「品質最優先」
改善方法:
社内イベントや研修で価値観を共有する
採用面接の段階で価値観の一致を重視する
行動指針をポスターや社内報で可視化する
事例:家具メーカーIKEAは「より多くの人々に快適な暮らしを」という価値観を全社員が共有し、店舗接客や商品企画に反映している。
5. Style(スタイル)
意味:リーダーの指導方法や社内の雰囲気。
例:
トップダウン型(上層部が決定)
ボトムアップ型(現場の声を吸い上げる)
改善方法:
定期的に社員アンケートを取り、組織の空気を把握
会議で上下関係にとらわれず意見を出せる場を作る
リーダー研修でコミュニケーションスキルを磨く
事例:あるスタートアップが週1回の「ノー上司会議」を導入。現場からの改善提案が急増し、新サービス開発のスピードが向上。
6. Staff(人材)
意味:社員の人数、スキル、配置。
改善方法:
戦略に必要な人材像を明確にする
採用と育成のバランスを取る
定期的な人事評価制度を見直す
事例:IT企業がクラウド技術者を重点採用し、クラウドサービス部門の売上を前年比150%に伸ばした。
7. Skill(スキル)
意味:組織や個人の持つ能力や専門性。
改善方法:
社内研修や外部セミナーの受講を推奨
スキルマップを作成し、誰が何をできるかを可視化
スキル不足分野を重点的に育成
事例:小売業が全販売員にSNSマーケティング研修を実施。1年でInstagram経由の売上が3倍になった。
「ハード」と「ソフト」はどこが違うの?なぜ両方大事?
ハード3S=比較的短期間で変えられる(組織図、システム、戦略)
ソフト4S=文化や人材で、変えるには時間がかかる
💡ポイント:どちらか片方だけ整えても成果は出にくい。戦略(ハード)に沿った価値観(ソフト)が根付くことで初めて組織は機能します。

「7Sモデル」を使って組織を改善する流れ
1. 現状分析(7つのSを一覧化)
目的:自社の現状を正しく把握し、どの要素が強みでどの要素が弱点かを洗い出すこと。
やり方
7つのS(戦略・組織構造・システム・価値観・スタイル・人材・スキル)それぞれについて現状を書き出す
定量的データ(売上推移、離職率、KPI達成率など)と定性的情報(社員の意見、顧客満足度など)をセットで確認
部署別にアンケートやヒアリングを行い、経営層だけでなく現場の声も反映させる
ポイント
書き出す際は事実と意見を分ける
「できていること」と「課題に感じること」を両方記載する
表やマトリクスにまとめると可視化しやすい
事例:ある製造業では、戦略と組織構造は明確だったが、スキル(Skill)の項目で「最新機械の操作を習得している人材が2人しかいない」という弱点が発覚。この後の改善計画で重点育成項目に設定した。
2. ズレの特定(要素間の不一致を見つける)
目的:7つのSの間で起こっている不一致やミスマッチを明確化し、問題の根本原因を特定すること。
やり方
各要素を横断的に比較
例えば「戦略(Strategy)」と「人材(Staff)」を比べ、戦略を実行するための人材が足りているかを確認
「システム(System)」と「スタイル(Style)」の関係を見て、制度があっても運用されていない原因を探る
ポイント
1つの要素だけを見るのではなく、要素同士の関係を見る
ズレは「リソース不足」か「方向性の不一致」の2パターンに分類できる
ズレを特定したら、影響度の大きい順に優先度をつける
事例:IT企業が新しい戦略で「海外市場拡大」を掲げたが、Staff(人材)の英語力が不足し、Shared Value(価値観)も国内市場重視のままだった。このズレにより、戦略の実行が遅れていた。
3. 改善計画作成(ハードから手を付け、ソフトも徐々に改善)
目的:ズレを解消し、組織全体のバランスを整えるための具体的アクションプランを作ること。
やり方
短期改善:ハードの3S(戦略・組織構造・システム)から着手
戦略の再設定、組織再編、業務ルール改善など
中長期改善:ソフトの4S(価値観・スタイル・人材・スキル)を強化
社内研修、価値観浸透施策、リーダー育成など
改善の進捗を定期的にモニタリングし、必要に応じて軌道修正
ポイント
「短期で成果が出る施策」と「長期で根本改善する施策」を両立させる
改善計画には担当者・期限・評価基準を明確に記載
小さな成功事例を社内で共有してモチベーションを維持
事例:サービス業の企業が、まずはSystem(顧客管理システム)を導入し、業務効率を短期間で改善。その後、Shared Value(顧客第一主義)を浸透させるために全社員研修を半年間かけて実施した結果、顧客満足度が15%向上。

初心者でもできる!7S改善の3ステップ【具体例付き】
ステップ1:現状を可視化(表やマップ化)目的:自分たちの組織が「7つのS」の各要素で今どんな状態かを整理し、強みと弱みを見える化する。
やり方
7Sチェックリストを作る
戦略(Strategy):目標や方針は明確か?
組織構造(Structure):役割や責任分担は明確か?
システム(System):業務ルールは機能しているか?
共通の価値観(Shared Value):理念は全員に浸透しているか?
スタイル(Style):リーダーシップや社風はどうか?
人材(Staff):必要な人数・スキルの人材が揃っているか?
スキル(Skill):組織や個人の能力は十分か?
表形式またはマインドマップで整理
各項目について「できていること」「課題」を左右に書き出す
可能であれば数値データ(売上、離職率、顧客満足度など)も添える
ポイント
1人でやらず、経営層・中間管理職・現場の代表など複数の視点を反映させる
感覚だけでなく事実ベースで記入する
事例:中小製造業A社では、7Sマップを作成したところ「戦略と価値観は共有できているが、システムが紙ベースで非効率」という課題が一目でわかり、改善の優先順位が明確になった。
ステップ2:弱点の特定(数値+現場ヒアリング)目的:「何が一番の課題か」「どこから手を付けるべきか」を明確化する。
やり方
定量分析:数値データから弱点を見つける
例)売上は伸びているが、離職率が高い=人材面(Staff)に課題
定性分析:現場ヒアリングやアンケートで現実の声を集める
例)「会議が多すぎて業務時間が足りない」という声=システム(System)の改善が必要
弱点の影響度を評価
「売上に直結」「顧客満足度に影響」など影響が大きい順に優先度を付ける
ポイント
弱点は「1つだけ」に絞らず、短期改善できる課題と長期的に取り組む課題に分ける
ヒアリングは匿名で行うと本音が出やすい
事例:サービス業B社では、「顧客対応マニュアルが部署ごとにバラバラ」というシステム面の弱点が発覚。影響度が高かったため、最優先でマニュアル統一プロジェクトを立ち上げた。
ステップ3:改善と検証(Before/Afterで効果測定)目的:改善施策を実行し、その効果を数値や現場の声で検証する。
やり方
改善計画の立案
短期改善:ハードの3S(戦略・組織構造・システム)を優先
中長期改善:ソフトの4S(価値観・スタイル・人材・スキル)を徐々に整備
担当者・期限・評価基準を明確に
実行とモニタリング
施策を小規模から試す(テスト導入)
定期的に数値とフィードバックを確認
効果測定(Before/After)
施策前後の数値比較(売上、工数、顧客満足度など)
社員アンケートで体感変化を把握
ポイント
小さな改善でも必ず成果を見える化し、社内に共有
効果が薄い場合は早めに軌道修正する
事例:小売業C社では、在庫管理システムを導入(Systemの改善)したところ、棚卸時間が半減。さらに社員研修で価値観(Shared Value)を共有し、顧客満足度が向上した。

よくある質問
Q1. 組織マネジメントの7Sとは何ですか?A. 「7S」とは、マッキンゼーが提唱した組織分析のフレームワークです。Strategy(戦略)・Structure(組織構造)・System(システム)・Shared Value(共通の価値観)・Style(スタイル)・Staff(人材)・Skill(スキル)の7つの要素を総合的に整えることで、組織の力を高めます。
Q2. ハードの3Sとソフトの4Sの違いは何ですか?A.
ハードの3S(戦略・組織構造・システム)は、比較的短期間で変更しやすい外側の仕組みです。
ソフトの4S(価値観・スタイル・人材・スキル)は、組織文化や人に関わる部分で、改善に時間がかかります。両方をバランス良く整えることが大切です。
Q3. 7Sモデルはどんな企業に向いていますか?A. 業種・規模を問わず活用できます。特に、
新規事業を始めるとき
急成長で組織が追いついていないとき
部署間の連携が悪いと感じるときに効果的です。
Q4. 7Sの要素を改善する順番はありますか?A. 一般的にはハードの3Sから着手するのがおすすめです。戦略や組織構造を整えてから、価値観やスキルなどソフト面の強化を進めると、全体の方向性がブレにくくなります。
Q5. 7Sの中で一番重要な要素は何ですか?A. 中心となるのは**Shared Value(共通の価値観)**です。全員が同じ価値観を持っていないと、他の要素を整えても一体感が生まれず、成果が出にくくなります。
Q6. 7Sモデルはどのくらいの期間で効果が出ますか?A. ハード面は数カ月〜半年程度で変化が見られることがありますが、ソフト面は1〜3年程度かけて定着させるのが一般的です。
まとめ|組織マネジメントの7Sは組織改善の羅針盤
組織マネジメントの7Sモデルは、戦略(Strategy)・組織構造(Structure)・システム(System)・共通の価値観(Shared Value)・スタイル(Style)・人材(Staff)・スキル(Skill)の7つの要素を総合的に見直すためのフレームワークです。
ポイントは、
ハードの3S(戦略・組織構造・システム)は短期間で変更しやすい
ソフトの4S(価値観・スタイル・人材・スキル)は時間をかけて育てる必要がある
7Sは互いに影響し合うため、部分最適ではなく全体最適が重要
改善の流れとしては、
現状を可視化し(表やマップで整理)
要素間のズレを特定し(数値+現場の声)
ハードから改善しつつ、ソフトも強化(短期と長期を両立)
このプロセスを踏むことで、組織は一貫性のある成長戦略を描けるようになります。
まずは現状の7Sをチェックし、小さな改善から着手してみてください。それがやがて、大きな組織改革の第一歩になります。



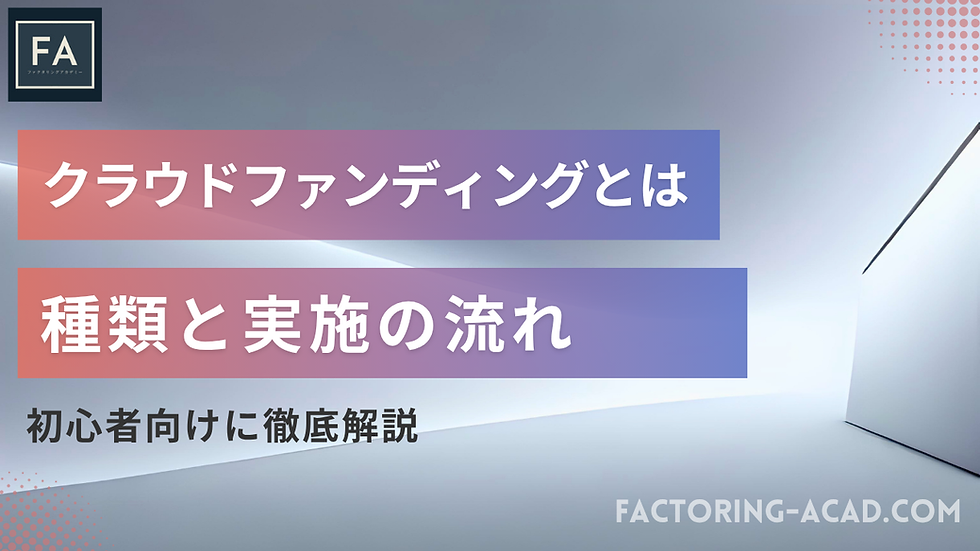

コメント