MBO(マネジメントバイアウト)のメリット・デメリット、MBOを成功させるためのポイントを解説
- FA

- 1月13日
- 読了時間: 14分

▼目次
MBO(マネジメントバイアウト)のメリット・デメリット、MBOを成功させるためのポイントを解説

MBO(マネジメントバイアウト)とは
MBOの定義と概要MBO(マネジメント・バイアウト)とは、企業の経営陣が自社の株式や事業を買い取り、経営権を取得する手法です。これにより、経営陣がオーナーシップを持ち、より主体的かつ長期的な経営判断が可能になります。
企業の成長戦略や事業承継の一環として行われることが多く、特に中小企業やファミリービジネスの後継者問題を解決する手段としても注目されています。
MBOが注目される背景近年、MBOが注目される背景には以下のような要因があります。
事業承継の選択肢の一つとして:少子高齢化の影響により、後継者不在に悩む企業が増加しています。MBOは、既存の経営陣が継続的に経営を担うことで、円滑な承継を実現できます。
短期的な株主利益からの脱却:上場企業においては、MBOを通じて非上場化し、長期的なビジョンに基づいた経営が可能になるケースもあります。
企業価値向上のための再構築:再編や事業再生の一環として、経営陣が自ら主導権を持つことで意思決定が迅速になり、企業価値の向上を図れる点が評価されています。
M&AやTOBとの違いMBOと混同されがちな手法として、M&A(企業の合併・買収)やTOB(株式公開買付)がありますが、目的や主体が異なります。
比較項目 | MBO | M&A | TOB |
主体 | 経営陣 | 外部企業・投資家 | 外部企業・投資家 |
目的 | 経営権の内部移行・承継 | 経営統合・事業強化 | 上場企業の買収・支配権取得 |
透明性 | 非公開で進むことが多い | 比較的公開される | 公開買付で透明性が高い |
実施企業の規模 | 中小企業にも多い | 大企業に多い | 上場企業が対象 |
MBOは、社内の信頼関係やノウハウを維持したまま、経営の独立性を強めることができる点が大きな特徴です。

MBOの主なメリット
MBO(マネジメント・バイアウト)には、経営の継続性やスピード感のある意思決定など、企業にとってさまざまなメリットがあります。ここでは代表的な3つのメリットについて解説します。
経営の継続性と事業承継がしやすいMBOは、現在の経営陣がそのまま企業を引き継ぐため、事業のノウハウやビジョンが継続されやすいという特徴があります。特に中小企業においては、後継者不足が大きな課題となる中、MBOは「外部に売らずに事業を守る」選択肢として有効です。
従業員の雇用や取引先との関係性も維持しやすく、混乱を最小限に抑えた承継が可能。
経営スタイルや社内文化を保ったまま次世代にバトンタッチできる。
意思決定のスピードが向上する経営陣がオーナーとしての立場を持つことで、社内の意思決定がより迅速になります。特に株主からの制約が少ない非上場企業の場合、長期的な視点に立った柔軟な経営戦略を実行しやすくなります。
経営判断が現場に近いところで行われるため、スピーディーな対応が可能。
中長期の経営戦略に集中でき、目先の業績だけにとらわれない運営が実現。
従業員や顧客との信頼関係を維持しやすい外部企業による買収と異なり、MBOは社内の経営陣が事業を引き継ぐため、従業員や顧客にとっても安心感があります。組織にとって“顔なじみ”のリーダーが継続して経営を担うことで、社内外の信頼関係を壊すことなく事業を推進できます。
突然の経営者交代による社内動揺を防げる。
顧客・取引先に対しても「これまで通り」という安心感を提供できる。
MBOのデメリットとリスク
MBOは多くのメリットを持つ一方で、実施にあたってはいくつかのリスクや課題も伴います。ここでは、MBOにおける代表的なデメリットと注意点を解説します。
資金調達のハードルが高いMBOでは、経営陣が自社株式を買い取るため、多額の資金が必要になります。自己資金だけでまかなうことは難しく、多くの場合、金融機関からの借入や外部投資家からの出資が必要です。
特に未上場企業や財務状況が芳しくない企業では、融資の審査が厳しくなる。
借入によって返済負担が重くなり、事業運営に制約を与える可能性がある。
経営陣のプレッシャーやリスクMBO後、経営陣は経営の責任者であると同時に出資者という立場になります。これにより、企業の成否が自分たちの資産に直結するため、大きなプレッシャーがかかります。
売上の変動や経済情勢によって、経営陣の個人リスクが高まる。
プレッシャーにより、短期的な利益を重視しすぎて本来の経営ビジョンがぶれる可能性も。
外部株主との利害対立が発生する可能性外部の金融機関や投資ファンドから資金を調達する場合、投資家と経営陣の間に利害のズレが生じることがあります。
ファンドが短期的なリターンを求める一方で、経営陣は長期的な経営を志向しているケース。
経営の自由度が制限されたり、意見の不一致から経営上のトラブルが発生する可能性も。
MBOは企業にとって魅力的な選択肢である一方、失敗した場合のインパクトも大きいため、事前のリスク分析と専門家のサポートが不可欠です。

MBOを成功させるためのポイント
MBO(マネジメント・バイアウト)を成功させるには、単に株式を取得するだけではなく、その後の経営を見据えた入念な準備と戦略が必要です。ここでは、MBOを円滑かつ効果的に実現するための重要なポイントを解説します。
明確な経営戦略とビジョンの共有MBO後の企業は、従来以上に経営陣の意思決定とリーダーシップが問われます。そのため、将来に向けた明確なビジョンと経営戦略を事前に整理し、社内外と共有しておくことが不可欠です。
中長期の収益計画や事業成長の方針を明文化しておく。
従業員や取引先に「この会社はどこへ向かうのか」を明確に伝えることで、不安や混乱を最小限に抑えられる。
適切な資金調達のスキーム構築MBOでは多額の資金調達が必要となるため、資金の出どころや返済計画を明確にしておく必要があります。以下のような複数の資金源を組み合わせるケースも一般的です。
財務の健全性と持続可能な返済計画を両立させることが、MBO成功の土台となります。
外部専門家(FA・弁護士・税理士など)の活用MBOは法務・税務・財務など複雑な専門知識が求められるため、外部の専門家を早期に巻き込むことが重要です。
ファイナンシャル・アドバイザー(FA):全体設計や資金調達支援を担当
弁護士:契約書の作成・法的リスクのチェック
税理士・公認会計士:税務処理や企業価値算定など
信頼できる専門家チームを組むことで、トラブルを回避しスムーズに手続きを進められます。
従業員・取引先との関係維持の工夫MBOによる経営体制の変更は、社内外の関係者にとって大きな変化です。信頼を損なわないよう、誠実な説明と丁寧なコミュニケーションを重ねることが成功の鍵となります。
従業員には「待遇や方針の変更がないこと」などを明確に伝える。
取引先には継続取引を約束し、安心材料を提供する。
組織の安定があってこそ、MBO後の経営も軌道に乗ります。
MBOの一般的な流れと手続き
MBO(マネジメント・バイアウト)を円滑に実施するためには、あらかじめ全体の流れを把握し、段階ごとに適切な対応を行うことが重要です。ここでは、一般的なMBOの手続きのステップを順を追って解説します。
1.事前準備(財務状況・ビジョンの確認)まずは、現経営陣がMBOを実施すべきかどうかの判断材料を整理します。
会社の財務状況や資産構成を明確にする
企業価値の算定(バリュエーション)を行う
MBO後のビジョンや経営計画を立案
また、社内外の関係者への影響も想定して、慎重に検討を進める必要があります。
2.買収計画の策定と合意形成次に、MBOの実行計画を策定し、関係者と基本的な合意を形成します。
買収対象(株式・事業単位など)と価格の設定
売却側(オーナーや株主)との基本合意(LOI:意向表明書)
社内への初期説明と理解促進
この段階では、弁護士やFA(ファイナンシャル・アドバイザー)を交えて、法的・実務的な整合性を確認します。
3.資金調達と契約締結合意内容をもとに、実際の資金調達を行い、契約を締結します。
銀行融資、投資ファンド、自己資金などの調達方法を確定
買収契約書(SPA:株式譲渡契約書など)の作成・締結
必要に応じてデューデリジェンス(資産・法務調査)を実施
資金調達は、MBO成功の可否を左右する重要なプロセスであり、慎重な計画が求められます。
4.クロージングと経営移行資金が準備できたら、クロージング(取引完了)を実行し、経営権を移行します。
株式の譲渡手続き(登記や名義変更)
経営体制の変更届や各種官公庁手続き
社内体制の再整備と従業員への説明
この段階で新体制をスタートさせ、事業運営をスムーズに移行させるための社内外への周知が不可欠です。

MBOにおける資金調達方法の選択肢
MBO(マネジメント・バイアウト)を実行するうえで最も大きなハードルのひとつが「資金調達」です。自社株式や事業資産を取得するためには多額の資金が必要になるため、MBOを検討する際には、適切な調達手段を選ぶことが重要です。
以下に、代表的な資金調達方法を紹介します。
自己資金・社内留保の活用まず基本となるのが、経営陣自身の資金による調達です。
自己資金で全額を賄うことは難しいものの、一定の金額を用意しておくことで交渉時の信用力が高まります。
社内に蓄積された利益剰余金や役員貸付を活用するケースもあります。
ただし、自己資金だけでは足りないことがほとんどのため、他の手段と組み合わせるのが一般的です。
銀行融資(LBO:レバレッジド・バイアウト)MBOの資金調達で広く活用されているのが、銀行などの金融機関からの借入れです。特に、買収する企業の資産や将来のキャッシュフローを担保に借り入れを行う「LBO(レバレッジド・バイアウト)」が代表的です。
買収対象企業の収益性が高い場合に有効。
融資条件として、明確な返済計画や担保設定が必要。
財務レバレッジが高くなるため、返済リスクにも注意が必要です。
投資ファンド(PEファンド・VC)からの出資資金規模が大きいMBOでは、プライベート・エクイティ(PE)ファンドや**ベンチャーキャピタル(VC)**など、外部投資家からの出資を受けるケースもあります。
出資により資金調達のハードルを大幅に下げることが可能。
一定期間後のEXIT(売却や再上場)を前提とした経営が求められる。
経営方針に関して、投資家との意見調整が必要になる場合も。
ファクタリングやABL(資産担保融資)の活用短期資金や補助的な資金源として、売掛債権を現金化するファクタリングや、**在庫や機械設備を担保にするABL(Asset Based Lending)**も有効です。
柔軟かつ迅速な資金調達が可能。
信用力が低くても利用できるケースがある。
中小企業のMBOにおける実行性を高める手段として注目されています。
その他の支援機関・制度事業承継・引継ぎ支援センター:中小企業のMBOを支援する公的機関。
地域金融機関の事業承継ローン:MBOを対象とした特別融資制度。
補助金・助成金制度:条件を満たせば、事業承継支援の補助金を活用できる場合もあります。
MBOは資金調達戦略が成否を分けると言っても過言ではありません。複数の手段を組み合わせて最適なスキームを設計し、無理のない返済計画を立てることが成功のカギとなります。

MBOの成功事例・失敗事例
MBO(マネジメント・バイアウト)は、企業の経営権を経営陣が引き継ぐという点で非常に魅力的な手法ですが、その結果は企業によって大きく異なります。ここでは、実際のMBOの成功事例と失敗事例を通じて、成功の要因やリスクを具体的に見ていきましょう。
成功事例に学ぶ「共通の成功要因」事例1:老舗製造業が事業承継型MBOで成長路線へ
地方で60年以上続く製造業の企業が、後継者不在を背景にMBOを実施。現場をよく知る経営陣が事業を引き継ぎ、既存の顧客基盤と技術力を活かしながら販路を拡大。外部ファンドの支援を受けつつも、経営の主導権は維持でき、黒字経営を継続。
成功要因:
経営陣の強い当事者意識と明確な経営ビジョン
社内外との信頼関係の維持
無理のない資金調達スキームの設計
事例2:上場企業が非上場化のためMBOを実行
短期的な株主要求に悩まされていた上場企業が、長期戦略に集中するためにMBOを実施。MBO後は株主構成をシンプルにし、研究開発や新規事業にリソースを集中させることで企業価値が大きく向上。
成功要因:
MBOの目的が明確で、全ステークホルダーに丁寧な説明を実施
経営の自由度を高め、長期視点の経営を実現
優秀な専門家(FA・弁護士)の活用と透明性の高い手続き
失敗事例に見る「注意すべき落とし穴」事例1:資金繰りが破綻した中小企業のMBO
創業経営者から現経営陣がMBOを実施したものの、無理な借入による資金調達を行い、返済負担が経営を圧迫。想定していた売上が立たず、わずか2年で倒産に至った。
失敗原因:
無理なレバレッジ構造による資金調達
返済計画の甘さとリスク分析の不足
MBO後の経営計画が現実的でなかった
事例2:社内の信頼関係が崩れたMBO
従業員に十分な説明をしないまま、経営陣が密かにMBOを進行。MBO完了後、従業員の離職が相次ぎ、主要取引先との信頼関係も揺らぎ、業績が悪化した。
失敗原因:
情報開示の不足による従業員の不信感
ステークホルダーとのコミュニケーション不足
経営陣の自己中心的な判断
MBOを成功させるには、「資金」「ビジョン」「信頼」の3点をいかにバランスよく整備できるかがカギとなります。成功事例から学び、失敗事例を教訓にすることで、MBOの成功確率は大きく高まります。

MBOに関するよくある質問
Q1. MBOとM&Aの違いは何ですか?A.MBOは、企業の現経営陣が自ら株式などを買い取って経営権を取得する手法であるのに対し、M&Aは第三者(外部企業や投資家など)によって企業の統合や買収が行われる手法です。
MBOは経営の継続性や組織文化の維持がしやすい点が特徴で、内側からの承継とも言えます。一方、M&Aは外部からの経営交代にあたるケースが多く、統合後の組織変革が課題になることもあります。
Q2. 中小企業でもMBOは実施できますか?A.はい、実施可能です。むしろ、後継者不足に悩む中小企業にとって、MBOは有効な事業承継手段です。社長の右腕となる役員や現場の経営陣が後継者として株式を取得し、スムーズに経営を引き継ぐことができます。
近年では、中小企業を対象にしたMBO支援策や金融商品も充実しており、専門家のサポートを受けながら実行することでリスクも抑えられます。
Q3. MBOにはどんな専門家が必要ですか?A.MBOは、法務・財務・税務・資金調達など多面的な知識が必要なため、以下のような専門家を活用することが一般的です。
FA(ファイナンシャル・アドバイザー):MBO全体の設計と実行支援
弁護士:契約書や法的手続きの確認
税理士・会計士:企業価値評価や税務対策
金融機関・ファンド担当者:資金調達スキームの相談
経験豊富なチームを早期に編成することで、MBOの成功率を高めることができます。
Q4. MBOに向いていないケースはありますか?A.はい、以下のようなケースではMBOの実行に慎重になるべきです。
経営陣に経営継続の意思や能力が不足している場合
会社の財務状況が悪化しており、資金調達が難しい場合
外部の株主がMBOに強く反対している場合
MBOが企業と従業員にとって本当に最適な選択肢かを冷静に見極めることが大切です。
まとめ|MBOは経営陣の意思で未来をつなぐ手段
MBO(マネジメント・バイアウト)は、経営陣自らが経営権を取得し、企業の未来を自らの手で築いていくための力強い選択肢です。特に、事業承継や非上場化を通じた長期経営を志向する企業にとっては、「信頼の継続」と「経営の自由度向上」を両立できる有効な手段となります。
一方で、資金調達の難しさや経営責任の重さといったリスクも存在するため、事前の入念な準備と専門家の支援が不可欠です。
MBOの成功に必要なのは、以下の3つの要素です。
明確な経営戦略とビジョン
現実的で持続可能な資金調達計画
ステークホルダーとの信頼関係の構築
これらをしっかりと整備すれば、MBOは「企業の未来を守る最善の道」となるでしょう。
経営を次のステージへと進めたいとお考えの方は、ぜひMBOという選択肢を前向きに検討してみてください。


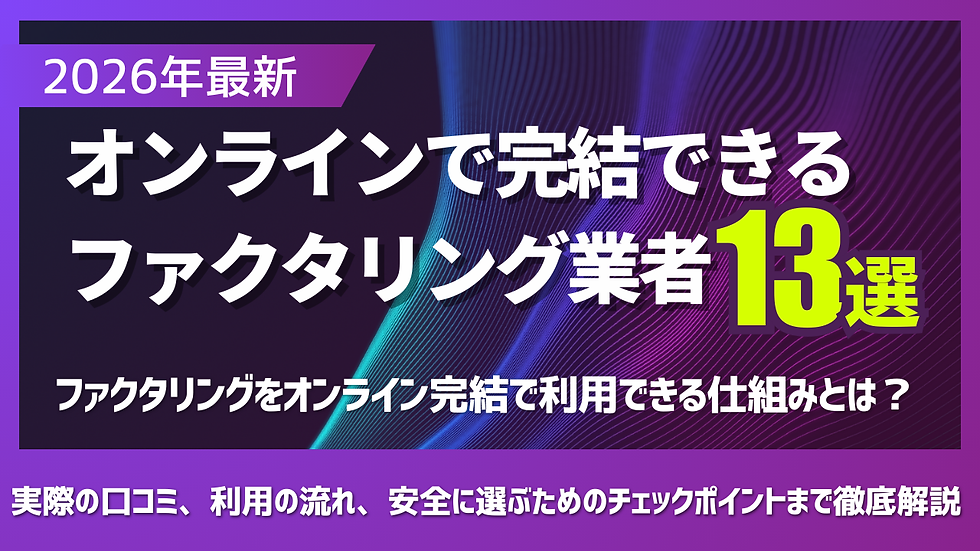


コメント